この記事は約10分で読めます。
時間のない方はこちらの3分要約版をご覧ください。
お金とはそもそも何でしょうか?これに対して、二つの答えが存在します。それが「商品貨幣論」と「信用貨幣論」です。
今回の記事では、両者についてわかりやすく解説した上で、両者を比較し、さらにどちらが正しいのかを考えます。結論として、より正しそうなのは「信用貨幣論」ですが、その理由を詳しく述べます。
 MMTanuki
MMTanuki商品貨幣論は主流派の経済学でしばしば語られてきたお金の見方だね。他方の信用貨幣論もそれなりの歴史があるけれど、最近、MMT派が自らの基礎として強く推しているからか、徐々に広まってきているみたいだね。
商品貨幣論―お金は誰もが受け取ってくれる価値ある商品(モノ)
「商品貨幣論」は、お金とは誰からも受け取ってもらえるような、非常に価値のある商品(モノ)だと考えます。
商品貨幣論では、商品同士が交換される物々交換経済が出発点に置かれます。
物々交換は非常に不便です。サカナが採れた私は、イノシシが欲しくて市場に向かいます。イノシシを持っているAさんがいましたが、Aさんはサカナは欲しくないので交換が成り立ちません。だから私はイノシシの肉が手に入らないまま家に帰りました。そんなことが頻発するわけです。
この失敗を反省した私は、市場に行く際には、ほとんど誰もが受け取りを拒否しないような、みんなにとって価値がある商品を持っていくことにしました。それは例えば、その社会で主食であるものでしょう。コメやコムギです。
この場合、コメはほとんど誰もが受け取りを拒否しないので、サカナと違い、それで何でも買うことができます。誰もが同じことを考えるので、コメが現代のお金と同じように機能し始め、だからこそコメがより一層受け取られやすくなります。
こうして物々交換のなかの商品の一つが貨幣の地位に上り詰めます。これが商品貨幣論です。さらに商品貨幣論は、この貨幣としての商品が最終的に貴金属(ゴールド・シルバー)に収斂したのだと考えます。それは劣化せず、さまざまな量に分割できる利点を持つからです。
信用貨幣論―お金は流通するようになった借用証書
「信用貨幣論」は、お金とは流通するようになった借用証書だと考えます。ここで信用(credit)とは、クレジットカードという言葉においてそうであるように、借金、貸し借りの関係、債権債務関係を意味します。だから、信用貨幣論とは、お金を借用証書とみなす考え方なのです。
信用貨幣論でも、商品取引を出発点に置くことができます。しかし、そこには物々交換は登場しません。どうなるのでしょうか。
先ほどと同様、私はイノシシが欲しくて市場に向かうとしましょう。ただ、今回は私はサカナなどの商品は持っていきません。強いて持っていくとすれば筆記用具です。
私はAさんからイノシシを買いますが、そのときに私は借用証書を渡すのです。「私はAさんからイノシシをいただきました。お返しにコレコレの日にコレコレのお返しをします」。これは要するに私はAさんに対して借りがあるということです。貸し借りの関係、債権債務関係、信用の関係が生まれているのです。
さて、この私の借用証書は、Aさんの私(と債務の執行を強制する社会制度)に対する信頼に基づいて発行されていますが、もし私(や社会制度)がBさんによっても信頼されていれば、Aさんは私が発行した借用証書を渡すことで、Bさんから何か、たとえば、モモなどを買うことができるでしょう。そして、Bさんもまた、Cさんから…。
こうして信頼に基づいて借用証書が流通するとき、それはお金になったといえるでしょう。これが信用貨幣論の考えるお金の起源となります。
商品貨幣論と信用貨幣論を比較する―価値のありか・時間との関係・有限性の位置
この二つの説を三つの観点で比較してみたいと思います。それを「価値のありか」「時間との関係」「有限性の位置」と名づけておきましょう。その意味は以下、それぞれの項目で説明します。
価値のありか―お金自体に価値があるか
さて、両説の違いの第一は、お金の価値をどこに見いだすかです。一言で言えば、商品貨幣論はお金自体に価値を認め、信用貨幣論はお金の価値は本来はお金自体の外部にしかないと考えます。
商品貨幣論は、お金を物々交換されていた商品のうちの一つとみなすことで、基本的にお金自体に価値があると考えます。もちろん、お金として機能するようになった商品は、その事実によって追加的な価値を持ちますが、それとは別に、お金は自らのうちに価値を持つ、少し難しい言葉を使えば、お金は内在的な価値を持つと考えるわけです。
対する信用貨幣論では、お金は借用証書であり、要するに紙切れであって、それ自体には本来価値はありません。価値があるのは、その借用証書に書かれている債務が履行されること、例えば、そこで引き渡すとされている何らかのものが実際に引き渡されることです。お金の価値は、それが指示している債務の履行、例えば、何らかのものの引き渡しにあります。お金は外在的な価値しか持たないわけです。
時間との関係―即時決済か時間をまたぐ取引か
第二に、商品貨幣論と信用貨幣論では、それがかつてあったと想定する商品取引の形が違っています。一言で言えば、商品貨幣論は即時決済をモデルとしていますが、信用貨幣論は時間をまたぐ取引をモデルとしているのです。
商品貨幣論は、お金の起源に物々交換を想定していました。信用貨幣論がモデルとする商品取引と比べた場合、物々交換の特徴は、それが即時決済であることです。価値のある商品に対して、別の価値のある商品がその場で即座に引き渡され、取引が終了します。そこでは相手に対して、その場で暴力を振るってこないという以外のいかなる信頼も必要としません。
対する信用貨幣論では、モデルとして時間をまたぐ商品取引が想定されています。価値のある商品に対して、引き渡されるのは借用証書という紙切れであり、価値ある商品の引き渡しは延期されます。ここでは、相手に対して将来の引き渡しというより高度な信頼が必要です。
有限性の位置―お金は有限か
第三に、両者はお金を有限とみなすかどうかの違いがあります。
商品貨幣論では、お金自体が商品となるモノですから、それは当然に有限です。ゴールドの総量は限られています。コメだって、いきなり無限に作り出すことはできません。
対する信用貨幣論では、お金の本体はモノではなく貸し借りの関係ですから、それ自体に量的な制限はありません。貸し借りの関係の成立によって、お金は増え、その解消によってお金は減ります。お金の量に物理的な制約はなく、制約は貸し借りで生じる債務の履行が期待されるかどうかにあります。
このようなお金の増減は、現代社会において「誰かが銀行から借金をすることでお金が生まれ、誰かが銀行に借金を返済することでお金が消える」「信用創造」という仕組みに対応しています。「信用創造」については以下の記事をご覧ください。


どちらが正しいのか―歴史・理論・制度という三つの観点で考える
最後に、商品貨幣論と信用貨幣論のどちらが正しいかを考えてみましょう。そのために歴史・理論・(現代の)制度という三つの観点から考察してみます。
歴史の観点とは、お金の起源やその後の発展の歴史と合っているのはどちらかという観点です。これについては近年、文化人類学の成果が、商品貨幣論が前提する物々交換が大規模に行われていた例がないことを示しつつあります。
また人類最古の文明であるシュメール文明における最初期の文字使用例が、まさに貸し借りの記録の帳簿であることが、信用貨幣論にとって事情を有利にしています。信用貨幣論にとって、本質は貸し借りの関係にあり、それが借用証書という形で切り出されて流通することで、お金が生まれるのです。
理論の観点とは、どちらがお金の理論として整合性があるのかという観点です。信用貨幣論の創始者の一人であるイネスが指摘したことですが、商品貨幣論には、コメが商品貨幣になったとして、コメを買うにもコメを払うのかという問題があります。
商品交換の中の一商品が貨幣になると考えると、この矛盾が生じてしまうのです。この矛盾を解消するには、お金はすべての商品に対して上位のレベルに立つべきなのですが、商品貨幣論では、お金自体が商品の一つであることで、この上位性が確保されないのです。
また、物々交換の歴史的な証拠がないこととも関連して、物々交換があまりに不便であり存在しそうにないことも、商品貨幣論の弱点となります。物々交換はもともとほとんど存在せず、もともと貸し借りの関係を通じた時間を隔てた取引、いわば信用貨幣的に取引が行われていたと考える方がよさそうなのです。
最後に(現代の)制度の観点とは、どちらが現代のお金の仕組みに合っているかしかという観点です。お金をゴールドという商品に紐づける金本位制が終了した現代において、商品貨幣論は現実の制度とまったく適合していません。他方の信用貨幣論は、現代のお金が、もっぱら信用貨幣の発展形である銀行預金から成っているという事態にピッタリと符合しています。
このように商品貨幣論と信用貨幣論を比較すると、信用貨幣論の方が貨幣の基礎理論としてより正しそうだと判断できるのです。
この記事のまとめ
この記事では、まずお金を商品の一つとみなす「商品貨幣論」と、お金の本質を貸し借りの関係のうちに見て、お金とは流通するようになった借用証書だとみなす「信用貨幣論」とを紹介しました。
続いて、両者の違いをさまざまな観点から比較しました。
その結果、「商品貨幣論」によれば、お金はそれ自身で価値のある有限なモノであり、それは物々交換のような即時決済の取引モデルを想定していることが明らかになりました。
他方、「信用貨幣論」によれば、お金はそれ自身には価値がなく、貸借関係の成立と消滅に応じて、自在に増えたり減ったりすることが明らかになりました。それが想定する取引モデルは、物々交換の困難を、信頼を通じて取引に時間差を設けることで回避するものだとわかりました。
最後に、両説のどちらがより正しそうかを検証しました。歴史的な証拠に合致するか、理論として矛盾がないか、現代のお金と整合的か、どの観点でも「信用貨幣論」に軍配が上がり、こちらのほうがお金の基礎理論として優れているとの結論になりました。
MMTanukiと暗渠づたいおじさんの余談—信用貨幣の弁証法に向かって



この記事では「商品貨幣論」と「信用貨幣論」を完全に対立させる形で論じているけど、それは本当に正しいのかな?信用貨幣論だと、たとえば「Aさんにイノシシをいただいた。お返しに秋にサンマをお返しする」といった借用証書がお金だとされているわけだけど、紙切れに過ぎない借用証書の価値は、記事でも明らかにされている通り、最終的にはサンマが引き渡されることに依存するわけだよね。このサンマは商品なんだから、結局、信用貨幣論も商品貨幣論であり、その派生系とも言えるんじゃないかな?借用証書は商品の代用物だと。それこそ、金本位制のもとでの紙幣が金の代用だったみたいに。



鋭い指摘だね。確かにある意味ではそうなんだけど、信用貨幣の本質のうちに、それが自らの外部にある商品への依存から自立しようとする運動が属していると僕は思っている。そもそも、信用貨幣論では、お金は「流通するようになった」借用証書とされていたでしょ。このことの意味は、借用証書が発行者のところに持ち込まれて、債務の履行、商品の引き渡しがなされるのではなく、借用証書が人々の間を転々として、さまざまな取引を媒介していくということだよね。債務の履行が延期されること、つまり、外部の商品からの一定の自立性を確立することによってのみ、借用証書は信用貨幣として機能するんだ。



へぇ、面白い話だけど、何やら抽象的というか、哲学的になってきたねぇ…。それにしても、「外部にある商品への依存から自立しようとする運動」っていうのは、どういうこと?



単にそもそも信用貨幣が成立するためには商品からの自立性がないといけないというだけではなく、信用貨幣はこのような外部への依存性を断ち切るために、徐々に発展していったというか、進化していった、そういう運動があったと考えているんだ。それが銀行と振替決済システムの成立に繋がったし、さらに中央銀行制度の成立に繋がった。信用貨幣は外部の実物への依存という自らの弱点を克服するために常により高次の形態へと進歩していったんだ。以前、別のブログでこのことを論じたことがある。そこでは、この「運動」を僕は「信用貨幣の弁証法」と呼んだよ。かなり専門的な議論になるけど、それは僕にとってはMMT派の貨幣論をまさに哲学的に肯定しぬくための議論になっている。このサイトでも、いずれまた論じ直すつもりだよ。



うーむ、なんか難しそうだけど、MMTを肯定できる議論なら、MMT派の僕も頑張って読んでみる価値がありそうだね。
余談で出てきた「信用貨幣の弁証法」の立場から、「信用貨幣論」と「信用創造」の関係を明確化する記事を書きました。信用創造の記事と併せてご覧いただけますと幸いです。また、「信用貨幣の弁証法」の全体像を提示した「MMTの貨幣の哲学」は本サイトの信用貨幣論関係の記事の総決算です。こちらも併せてご覧いただけますと幸いです。




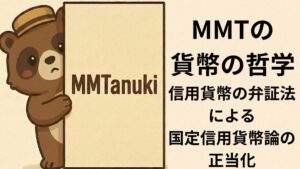
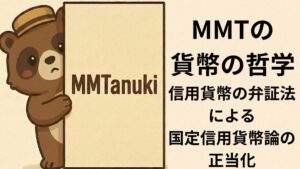
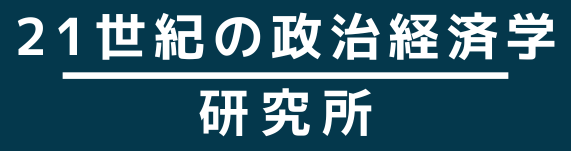

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます