この記事は約16分で読めます。
時間のない方はこちらの3分要約版をご覧ください。
この記事ではフェリックス・マーティンの『21世紀の貨幣論』は要約と解説を行います。
本書は今後の貨幣についての議論がまずは参照すべき基本図書です。以下では理論編・歴史編・政策編に感想編を加えて、要約と解説を行います。
 MMTanuki
MMTanuki僕もこの本はMMT派のための貨幣の歴史の本として読んで重宝しているよ!



僕もこの本は歴史編が一番好きだな。モンテスキューの話とか「マネーの大和解」とかロックの役割とか、面白い話が多いよね。
理論編:商品貨幣論から信用貨幣論へ
本書のポイントの一つは、主流派経済学の貨幣論であり、世間一般でも広く受け入れられている商品貨幣論の批判し、貸借関係を基礎とする信用貨幣論を主張する点です。これがいわば本書の理論編にあたります。
商品貨幣論とは、「貨幣は、ゴールドやシルバー、あるいは古くはコメや塩や布といった、それ自身が商品であるものの一種だ」という貨幣観です。それによれば、貨幣は、物々交換の不便さを解消するために、物々交換されていた商品のうちの一つが、商品交換のための道具として選び出されることで生まれます。
だが、近年、人類学などの実証的な研究において、この商品貨幣論の出発点に置かれている物々交換の社会が、どうも歴史的に大きな規模では存在しないのではないかということが明らかになってきています。
それに加えて、1971年にドルとゴールドとの交換が打ち切られて、貨幣をゴールドに結びつける金本位制が最終的に終わり、貨幣が何らかの商品に物理的に裏付けられることのない「単なる紙切れ」としての紙幣になっているという事情もあります。さらに銀行口座や証券口座の残高という電子的な数字こそがますます貨幣の中心になるに及んで、貨幣を商品である何らかのモノとして考えることが、現代にあって、ますます無意味になってきています。
こういった状況を踏まえ、マーティンは貨幣を商品とする商品貨幣論を、貨幣の根本的な定義としては否定し、貨幣のより根本的な定義、信用貨幣論的な定義を提起します。
この[商品貨幣論とは別の]もう一つの貨幣論の中心にあるもの、原始概念と言っていいものは、信用だ。マネーは、交換の手段ではなく、三つの基本要素でできた社会的技術である。基本要素の一つ目は、抽象的な価値単位を提供することである。二つ目は、会計のシステムだ。取引から発生する個人や組織の債権あるいは債務の残高を記録する仕組みのことである。そして三つ目は、譲渡性である。元債権者は債務者の債務を第三者に譲り渡して、別の債務の決済にあてることができる。
『21世紀の貨幣論』p40 [ ]内部と太字は引用者の補足
この定義を見ていきましょう。「信用」に関しては、いったん後回しにします。
第一、「抽象的な価値の単位」について。これは貨幣の前提は互いに全く異なるさまざまなものの価値が一つの単位で測られるようになるということにある、ということを言っています。
たとえば長さの単位は物理的なモノにしか適用されませんが、現代において円やドルという貨幣単位は、商品であるモノにも、非物理的なサービスにも、あるいは、損害賠償において、間接的にではあれ、「命」にまで適用されます。貨幣が存在するためには、このように(ほとんど)あらゆるものに適用される抽象的・一般的な価値という観念がまずは必要だということです。
第二、「会計のシステム」について。これは貨幣が機能することには、物理的なモノは必ずしも必要ではなく、誰がどれだけプラス(他者に対して「貸し」がある)で、誰がどれだけマイナス(他者に対して「借り」がある)なのか、その残高と変化を記録する仕組みこそが本質的だということを言っています。
このような記録があれば、多くの取引は物理的な貨幣なしに帳簿上のプラスとマイナスの相殺処理で清算できます。なんらかのモノが貨幣として機能しているように見えても、それはその実、この相殺処理で残った残余の部分の清算のために譲渡されているだけだということも多いというのです。商品貨幣より本質的なのは会計のシステムというわけです。
第三、「譲渡性」について。これは最初に出てきた「信用」と繋げて「譲渡性のある信用」と読まなければいけません。ここに続く箇所で、マーティンは「マネーは単なる信用ではない。譲渡することが可能な信用なのだ」(p41)と宣言しています。
以上の三つを合わせて考えると以下のようになります。
まず、抽象的・一般的な価値単位が観念され(第一の要素)、その単位でもってさまざまな取引が帳簿に貸し借りとして記録されます(第二の要素)。この貸し借りが、すなわち、信用です。相手の支払い(能力)を信用して、私たちは相手に貸し、その貸しを帳簿に「つけ」ておきます。実際、信用と訳されているcreditを手元の英和辞典で引くと、最初に「つけ」と出てきます。昭和の飲み屋でよく聞かれたらしい、「つけといて!」という、あの「つけ」です。
この「つけ」というのは、一種の借用書です。この借用書が流通するとき、それは単なる信用からマネーへと変化します(第三の要素)。
例えば、Aさんが私を信用していれば、「私はAさんにコレコレの借りがあるので、コレコレの期日までにアレソレをお返しする」という借用証書でもって、私はAさんに何か財やサービスを提供してもらうことができます。そして私がBさんにも信用されているのであれば、この私の借用証書を渡すことでAさんはBさんに何か財やサービスを提供してもらうことができるでしょう。Bさんはそれを私のところに持ってきてお返しを貰えばいいと思うわけです。こうして借用証書は譲渡性を帯びることでマネーとして機能するというわけです。
以上が本書の考えるマネー・お金の根本的な定義、信用貨幣論的な定義なのです。ここで信用とは貸し借りの関係のことで、最終的にお金とは、一般的な価値の単位を利用する、貸し借りの関係から発行され、譲渡可能になった借用証書と定義されます。
歴史編:国家と銀行の千年戦争、マネーの大和解、ロックの一撃、そしてマネーの現代へ
続いて、本書のいわば歴史編を見ていきましょう。それを簡単にまとめれば、以下のようになります。
まず理論編で紹介したマネーの前提要素の一と二が、それぞれ古代ギリシャとメソポタミアで出現し、古代においてマネーが成立したとされます。メソポタミアの官僚制が会計システムを準備し、ギリシャの部族の、成員男性は等しく社会的価値を持つという観念が、普遍的・抽象的な経済的価値の観念に発展したのだというのです
その後、中世から近世にかけては、三の要素に関連して、高い信用力を持つ国家と銀行が貨幣の発行とその価値の管理をめぐって争い、それは1694年のイングランド銀行の設立、すなわち、初めての近代的な中央銀行の設立で決着します。国家と銀行が和解することになるのです(両者の戦いについて詳細は3節で述べます)。
これがマネーの近代の始まりを規定する、マーティンが「マネーの大和解」と呼ぶ出来事です。
だが、この和解が達成されてすぐ、また別の勢力が襲いかかってきます。それはロックの一撃ともいうべきもので、ジョン・ロックが提唱した銀本位制論です。それは銀というモノをこそ真の貨幣とする商品貨幣論で、通貨の切り上げや切り下げ等の、貨幣の価値の一切の人為的操作を否定して、ポンドと銀を不変の仕方で結びつけようとしました。ポンドとは一定量の銀に他ならず、その価値は不変であり自然だというわけです。
これが出発点となって、経済学では商品貨幣論が定説となり、制度面では金や銀の本位制が採用されていきます。そうして貨幣の価値は、不変で自然であるとされ、大和解までは大いに操作され政治的に争われてきた貨幣の価値は、操作がされえないもの、政治的にも経済的にも中立なものと化していきます。貨幣の自然化という魔法がかかったのです。
最後にマネーの現代を語るとすれば、二つのことが契機となります。一方では、ドルとゴールドの交換を打ち切り、金本位制を最終的に終わらせたニクソン・ショック、他方では、主流派経済学の信用を失墜させたリーマン・ショック(世界金融危機)です。商品貨幣論を暗に前提し、借金を通じてマネーが創造され、返済を通じてマネーが消滅するという、信用貨幣論に親和的な信用創造を理論に取り込んでいない主流派経済学には、この種の金融危機ないし恐慌を理解する能力がそもそもないのです。
こうしてマネーの現代においては、貨幣を自然化したロックの魔法が解けていきます。それは金本位制という制度面での支えも、主流派経済学の商品貨幣論という学問面での支えも失ったのです。そうして魔法のベールが剥がれれば見えてくるのは、そこにもともとあったもの、マネーの大和解という国家と銀行の和解が、現代の貨幣を支えているという現実です。
この現実を素直に表現しているのが、主権貨幣論と信用貨幣論を並列させる現代貨幣理論、すなわち、MMTということになります(※)。これがマネーの現代を特徴づける光景なのです。
(※)マーティンは、参考文献表の冒頭のところで、影響を受けた本として、MMTの主唱者のひとりであるランダール・レイの編著をあげ、レイを「経済分析にマネーを組み込むより現実的なアプローチを積極的に提唱し、それを広めることに長く尽力している」(索引・参考文献のp7)と評価しています。本書にMMTへの言及がないのは、本書が書かれた2013年には、まだそれがいまほど明確な形をとっていなかったからだと思われます。
3、政策編:貨幣の政治性を自覚し、民主政治でその価値の標準を統御する
最後に、本書が提案する政策の方向性を紹介しましょう。
その前提は貨幣の価値の政治性の自覚です。そもそも、マネーの大和解以前には国家と銀行がこれをめぐって激しく対立していました。
一方で、国家(君主)は貨幣の改鋳から通貨発行益を得ていました。それはたとえば一枚の硬貨を二枚に鋳直すといったことによってなされます。国家は最初の二倍の硬貨を得ますが、これは硬貨の量の増大によって、徐々にその価値の減価を引き起こします。それはモノの方から見れば物価高騰、すなわち、インフレが生じるということです。
とすると、この改鋳を経ても一枚の硬貨が一枚のままでしかない普通の人々の資産の価値と購買力は減少します。他方の国家は、はじめに二倍の硬貨を得ているわけですから、インフレが一気に起こるわけでもないこともあって、やはり得をするのです。君主は貨幣改鋳により、一般の人々から自身への再分配を実行していたのです。
これに反発したのが資産家たちです。ただ、反発をしても初めは徒手空拳でした。彼らが実効的に君主に対抗できるようになったのは、私的な信用を流通可能なものに変換する銀行システムが生まれ、それが外国為替相場を成立させることによってでした。モンテスキュー曰く…。
為替相場は世界のすべての貨幣を比較して、それを適正に評価することを銀行家に教えた…為替相場が確立されたため、君公が貨幣を突然、大きく操作すること、少なくともそうした強権の発動を成功させることはできなくなった。
『21世紀の貨幣論』p169
こうして君主は貨幣改鋳を封じられ、財源を確保するのに借金をすること(国債発行)を強いられるようになりました。中央銀行とは、銀行が君主の国債を引き受ける代わりに、君主が銀行に国家の信用を与えるという妥協の産物であり、中世から対抗関係にあった国家と銀行との大和解だというわけなのです。
先に述べたように、このあとにロックにより貨幣が自然化されるわけですが、その前までは、貨幣とその価値は操作可能なものであり、極めて政治的なものだったわけです。それによって君主や資産家、そして一般庶民の利益と不利益が根本的に再配分されるからです。
マーティンの政策的な提案は、このロックによる自然化の魔法が解けた今となっては、ふたたびこの政治性を自覚することが重要であり、貨幣の価値の操作を、かつてのように君主の利益のために用いるのではなく、民主政治によって、多くの人々の利益となるように活用すべきだというものです。
それは具体的には基本的にインフレ的な方向性での調整を意味しています。現在は格差が行き過ぎており、富裕層は資産でお金を稼ぎ、貧困層はその資産の裏側にある負債で苦しめられています。いま必要なのはインフレによって債権の価値を下げ、債権者から債務者への再分配を実行することだというのです。
これはかなり急進的、革命的にみえるかもしれませんが、実際は、このような格差を放置することこそが、真に暴力的な革命への道を開くとマーティンは言います。状況がそこに至る以前に民主政治を通じて状況を改善することが、革命を防ぐ唯一の道なのだというわけです。
また、直近の世界金融危機(リーマン・ショック)に関しては、金融業界のリスクテイクに関して、利益は金融機関のもの、損失は納税者のものという不合理が生じていることを問題視しています。
こんなことが生じるのは、金融業界が信用創造という仕方でマネーの大部分の供給者となっているからです。マネーの供給者たる銀行の経営危機は、貸し渋りと貸し剥がしを通じて、マネーの消滅危機に繋がり、経済全体の完全なクラッシュを引き起こしかねません。なので国家は公金を投入して銀行を救済しなければならないハメに陥るのです。
これに対してマーティンが引き合いに出すのは、アーヴィング・フィッシャーの100%マネーの提案です。そこでは、銀行が二つに分割されます。一つ目は、100%の預金準備が課せられることで信用創造を禁止され、人々から集めた預金による決済業務に専念する決済預金銀行です。この種の銀行は、厳格な規制を受けるが、その代わりに政府による保護が受けられます。
もう一つが貸出を行う銀行で、こちらは投資家からお金を集金して、そのお金を投資する投資銀行です。こちらに関しては、信用創造も禁止されないようですが、そのような規制がない代わりに政府の救済はあり得ないと明確になっており、リスクは投資家が負うことになるとされます。
4、感想編:貨幣と貨幣論の政治性、その現在
さて、最後に私の感想を少し述べておきます。本書の読後に印象的なのは貨幣と貨幣論の政治性です。
マネーの大和解にいたるまで、一方では君主は人々から自身への再分配を実現するために貨幣改鋳をしたかったし、それで財産を実質的に奪われる資産家たちは、銀行を作って金融資本となり、外国為替市場の支配権を握ることで、それを牽制していました。
そして、マネーの大和解後には、ロックが財産を持つ人々を代表して、その財産が国家や銀行の恣意によって価値を失うことのないように、貨幣の価値を銀の一定量に固定しようと試みました。
これと全く同じ構図の争いが、現代でも繰り広げられているように思うのです。
すなわち、一方でMMTの影響を受けた積極財政的な議論がある程度は普通の人々に普及しつつある。これはもはや君主のためではなく人々のためであるとはいえ、系譜としては君主の貨幣論(貨幣国定説・主権貨幣論)の末裔でしょう。
他方で投資家や金融資本の関係者などは、この動きに外国為替等のマーケットの動向を持ち出して牽制することが多いような印象があります。たとえば銀行出身の石丸伸二氏などは、MMTだと「マーケットが持たない」などと(モンテスキューと同様に)主張しています。これは金融資本の末裔の系譜に属する議論といえるでしょう。金融資本にとっては、自身の持つ債権の価値が保存されることが本質的であり、国家の通貨発行は危険なのです。
(注:石丸伸二氏は経済の専門家を自称しているものの、「マーケットが持たない」が出てくるこちらの動画の11分以降の発言を見る限り、MMTを説明するという触れ込みで金融政策重視の主流派経済学風の説明をし、MMTのみならず主流派経済学すら知らないことを露呈しており、いかなる意味で経済の専門家なのかは不明です。ここで彼を引いたのは、変に知識がないだけに(金融資本の?)イデオロギーが純粋に露呈されているからです。)
ロックの末裔は、リバタリアンと称される人々でしょう。彼らはいまゴールドやビットコインに資産を移しているはずです。彼らにとっては貨幣は国家等によって量(価値)が変更され得ない、有限の自然物や人工的に有限性が設定されたもの(=ビットコイン)である必要があるのです。彼らにとっては商品貨幣論がベストなのです。
重要なことは、この貨幣論の政治性の帰結です。それは「議論」には限界があるという認識です。
MMTの貨幣論は、私の考えでは文句なく現代社会においてもっとも現実的なものですが、これを議論を通じて説得しようとしても限界があるように思うのです。というのも、それが不利益となる人々がいるからであり、そういう人々にとっては議論が正しいか正しくないかなど関係ないからです。
貨幣論が政治的であるとは、それが利益配分の問題に関わり、正しい正しくないでは解決できない問題であるということを意味します。
だから、貨幣論は、結局は広がるべきところへ広げるしかなく、広がりようもない相手に対しては最終的に数の力で押し切るしかない、そういうものなのかもしれません。
MMTanukiと暗渠づたいおじさんの余談①—MMT派のための貨幣の歴史?



僕はこの本をMMT派のための貨幣の歴史だと思って重宝してるよ。本文の繰り返しにはなるけれど、中世から近世にかけて、国家と銀行が貨幣をめぐって戦いを繰り広げ、それが中央銀行の創設というマネーの大和解で解決された。しかし、その直後からロックと主流派経済学の商品貨幣論と金本位制によるマネーの自然化で、この歴史と貨幣の実相が隠蔽されてしまう。ニクソン・ショックによる金本位制の終焉と世界金融危機での主流派経済学の信用失墜で、この自然化のヴェールで剥がれる。そこで見えてくるのが銀行と国家との和解が作り出す貨幣の現実であって、それを素直に叙述しているのがMMTだと考えられるよね。



まったく同意だね。MMTは要するに金本位制以後の貨幣論なわけだけど、でも、金本位制が終わって初めて有効になったものではなくって、もっともっと深い歴史的な底流に対応していて、むしろ、ロックと主流派経済学こそがその貨幣の本流に対する逸脱なんだという、そういうより深い見方を提供してくれていると思う。
MMTanukiと暗渠づたいおじさんの余談②—マーティンの政策をどう見るか?



ところでマーティンの政策提案はどう思う?やっぱり世界金融危機後だからか、政策提案のなかで銀行政策の占める割合が大きいよね。
提案の一つは、銀行がリスクの高い投資をやって、成功したら儲けは自分のもの、でも失敗しても潰せないから政府支援が行われて損失はみんなのものというのはおかしいから、銀行を二つに分けるって話だったね。政府がしっかり保護するけど、その代わりリスキーなことは全くできない貯蓄と決済専門の銀行と、規制が緩くてリスキーなこともやっていいけど完全自己責任な銀行。
もう一つは、お金の価値を基本的にインフレ的にすることで、債権の価値を下げ、債務の負担を軽くすることで、お金持ちの債権者と貧しい債務者との格差を縮小するってことだったと思う。お金の価値を計画的に下げることで、それがそもそも社会の中でお金があまり価値を持ちすぎないようにするっていう意図もあるのだろうね。



うーん、なんというか全体的に反対はしないけど、どうもちょっと自分とは問題意識がズレているって感じかなぁ。
僕としては、ケインズじゃないけれど、「豊かさの中の貧困」、いやもっと言葉を強めて「豊かさゆえの貧困」というものに非常に理不尽を感じていて、そこをまずはなんとかしたいなと思っている。
「豊かさゆえの貧困」というのはこういうこと。いまの経済ってめちゃくちゃ生産能力、供給能力が高まっていて、それに需要が追いついていないのが基本の状態だと僕は思っている。小野理論じゃないけれど、モノやサービスへの人々の需要は飽和気味で、人々はモノやサービスで得られるリアルな満足より、貯金や証券口座の残高が増えることにより満足を覚えるようになっている。だから潜在的な供給能力に匹敵するだけの需要がないんだよね。みんなモノよりお金の方が好きなんだから。
で、そうすると供給能力が余るわけだけど、それは労働力としての人間が余るってわけで、人間の過剰による失業・短時間就業・低賃金労働が生み出される。そうして貧困が生まれる。
これほど不条理なことはないよね、だって、有り余る供給能力という豊かさこそが、それに匹敵する需要が欠けているという理由によって、一部の人々を貧困に追いやり、また普通の人々に貧困に陥りたくないと過剰な競争を強いるわけだから。本来、生産能力の拡大によって頑張る必要が減っているのに、社会の構造がその変化に対応していないがために、人々が無意味な苦境や苦行を強いられるわけだ。
いまは人手不足が云々されているけど、それは局所的なものだと思うし、そうでないにしても一時的なもので、長期的には技術革新による省力化・自動化が勝って、この需要不足の傾向はますます強くなると思う。
だから、何も手を打たなければ「豊かさゆえの貧困」はますます深刻化して、自分が幸せだと思えない人が増えてしまうし、社会が不安定化していくんじゃないかと感じているよ。
この観点からは、あまりお金が価値を持ちすぎないようにインフレ的にするという提案には好意的だよ。それは人がお金を物に変えることを促し、需要創出的だからね。ただ、僕としてはみんなが存分に活躍できるだけの需要を作り出して完全雇用を達成する積極財政とか、あるいはそもそも生存と労働を切り離して貧困問題を解決しつつ労働供給を減らすことで供給過剰を終わらせるユニバーサル・ベーシックインカムとか、そういった政策論のうちの一つという位置付けで、政策の全体構成のなかで採用するべきかどうか検討する必要がある、くらいの感じかな。
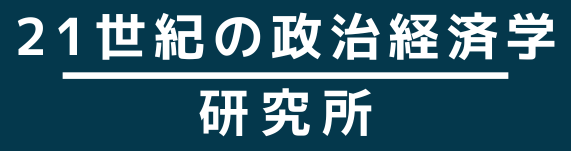


※コメントは最大500文字、5回まで送信できます