この記事は約16分で読めます。
この記事では積極財政派から日本の緊縮財政の根本原因としてしばしば批判される財政法の第4条について、分かりやすく詳しく解説します。
第1節では、財政法4条の内容を確認した上で、それに意義を認めて擁護する側と緊縮財政の原因として批判する側の基本的な見解を紹介します。
第2節では、その制定過程を調べることで、財政法4条が日本弱体化のためのGHQの陰謀かどうかを検証します。
第3節では、財政法4条が実は積極財政を可能にするべく制定されたもので「も」あったという意外な事実を明らかにします。
 積極グマ
積極グマえ?財政法4条が積極財政?てっきり緊縮財政の本丸、諸悪の根源だと思ってたよ!
財政法4条、左派からの擁護と右派からの批判—平和主義と緊縮財政
まずは財政法4条の条文を見てみましょう。
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
財政法4条の本文は、要するに、「国の借金」といわれる国債(公債・借入金)発行による財源調達を原則として禁止するものです。そうすることで「税金こそが基本的な財源だ」「歳出は税収の範囲内で行え」「借金はするな」と宣言するものとなります。
この条文の意義を認めて擁護する側は、私なりに要約すると、だいたい以下のように主張します。
この財政法4条は戦争の反省から生まれたものだ。第二次世界大戦で日本は他国にも自国にもひどい被害をもたらす戦争をしてしまった。それができたのは国債を発行し、それを日銀に引き受けさせることで、戦争のためのお金を無尽蔵に調達できたからだ。
日本は戦争を反省し、平和主義を三大原則の一つとする日本国憲法のもと、憲法九条によって戦争を放棄した。財政法4条は戦争に不可欠な国債による軍事費調達を不可能にすることで、「憲法九条の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするもの」なのだ。というのも、「公債のないところに戦争はない」からだ。
これがだいたい財政法4条擁護派の主張です。最後の二つのカギカッコ内のセリフは財政法制定に深く関わった大蔵官僚の平井平次が『財政法逐条解説』という本に書いている言葉で、この文脈でよく引用されます。
さて、この主張は、当然、平和主義を強く主張し、憲法9条擁護の観点から日本国憲法の改正に反対する護憲派からよく持ち出されます。日本共産党はこのような主張を肯定的に紹介し、朝日新聞も同様です。これはいわゆる政治的な左派、リベラルからよく行われる主張ということになります。
このような状況に対して、2010年代の後半から批判が起こり始めました。
この時期、いわゆる政治的な右派のなかで、平成の日本の経済停滞の原因を緊縮財政に見定め、それに反対して積極財政を求める運動が広がりはじめ、緊縮財政の根本原因としてこの財政法4条が発見されたのです。そこでは、私なりの要約ではだいたい以下のように主張されます。
日本の経済がずっと停滞してデフレを抜けきれないのは、経済に需要が足りないのに、政府が大胆に財政出動をして需要を作り出すのではなく、他の家計や企業と一緒になって節約に走り、需要を生み出すことをしないからだ。
日本の停滞の原因はこの緊縮財政にあり、その主犯は緊縮財政を推し進める財務省と、財務省にそれを強いている財政法4条だ。財政法4条が国債発行を原則として禁止しているからこそ、不景気で税収が減ると、政府も支出を切り詰めざるを得なくなる。こうして緊縮財政が行われ、不景気は長引き、また税収が落ち込んで、それがさらに…という悪循環が生まれるのだ。
こういうわけで財政法4条は日本を衰退させている悪法なのだが、憲法9条が大好きな左翼は、9条とセットだということで財政法4条もありがたがっている。やっぱり左翼は碌でもない。そもそも平和憲法がアメリカ・GHQの押し付けなのだから、それとセットの財政法4条もGHQからの押し付けではないか。
それは緊縮財政によって日本を衰退させようとするGHQの陰謀なのではないか…。財政法4条は、敗戦国日本を弱小国たらしめようとする戦後レジームの本丸なのである。
これがだいたい財政法4条を批判する右派積極財政論の主張ということになります。第2節では、ややマニアックですが、このGHQ陰謀論を検証します。最後に第3節では、実は積極財政を可能にすること「も」意図していたという財政法4条の意外な側面を見たいと思います。
財政法4条は日本弱体化のためのGHQの陰謀か—その制定過程を知る
さて、この財政法4条は日本弱体化のためにアメリカ・GHQによって仕組まれた罠なのでしょうか。これが完全に事実無根・荒唐無稽な陰謀論ではないことは、1988年の国会にて当時の大蔵大臣宮澤喜一が以下のように答弁していることからも明らかです。
財政法は、戦後時間のたたない時期につくられましたので、相当時間がたっておりますが、これがつくられましたときには、戦争というものについてのお互いの反省もあり、また戦敗国であった点もございます。結局、戦争中に国債がいわば自由といいますか無制限に発行できるということが日本が戦争に入った大きな原因であるという反省が我々の中にもございましたし、また占領者もそういうふうに考えたと思われますが、そういう雰囲気の中でできました。したがって、赤字財政ということはやってはならないという考え方が財政法を貫いておるのではないかと存じます。
財政法は、無制限の国債発行が戦争の原因だったという占領者(=アメリカ・GHQ)も共有していた考えが支配する雰囲気のもとで作られ、赤字財政の否定を原則としているというわけです。宮澤はわざわざ占領者に言及しています。
ただし、財政法制定過程のより仔細な検討は、財政法4条が日本弱体化のためのGHQの罠であるということに関しては、やはり否定的な結論を導き出します。冷戦の構造が明確化する前、戦後最初期の占領統治が日本の弱体化を目標としていたという点は否定し得ないとしても、そのために財政法4条の健全財政主義が押し付けられたわけではなさそうなのです。
なぜそう言えるのでしょうか。大蔵省・財務省の正史『昭和財政史』の第四巻には財政法制定の過程が詳しく述べられています。それは四段階に分けることができ、①1946年の臨時法制調査会における議論、②大蔵省内部での検討と法律案の起草、③GHQとの折衝、④国会での審議と成立、という経過を辿りました(p.111)。
今回、当然、注目したいのは③のGHQの折衝ですが、この内容についても本書は大蔵省文書や口述資料に基づき、再構成しています(p.124-128)。
それによれば、GHQとの折衝の結果、変更された主な点は以下の二点のみです。
第一は、アメリカの原理主義的な三権分立の考え方に基づいて、国会・裁判所・会計検査院の予算に関しては、内閣による予算決定から一定の独立性が確保されるべきだとされ、その点が条文に盛り込まれたこと。
第二は、大規模な工事など複数年度にわたる支出の総額を最初の年の予算に一括で盛り込むことができる継続費の制度が、GHQの強い反対で削られたこと。
後者に関するGHQの反対の根拠は、政治家が人気取りに走って継続費が膨張し、予算が硬直化する、つまり、継続費で予算がパンパンになり、その年その年の新しい課題に対応できなくなるというものだったとのことです。
この後者の点などは一定程度、緊縮財政的とは言えるものの、以上から分かることは、財政法4条自体がGHQによる押し付けだというわけではないということです。また、後者の継続費制度も、サンフランシスコ平和条約で日本が独立を回復すると、財政法が改正されて復活することになりました。そういう意味では、GHQの押し付けということがあったとしても、必要な部分はのちに改正されているのです。
これに対する反論としては、「いや、GHQは財政法4条みたいなものは作る気だったのだ!ただ、大蔵省が最初から財政法4条を作ってきたら、そういうことをわざわざ折衝では言わなかっただけだ!」というものがありうるでしょう。「そもそも、大蔵省草案の段階で圧力をかけて、財政法4条を作らせておいたのかもしれない」とも言われるかもしれません。
ただ、これもそれほど説得力はない議論です。というのも、財政法の上位に位置する憲法改正についてのGHQの基本指針を示す文書SWNCC-228では、財政制度に関する重点は「議会中心主義の強化と、とくに皇室財政にたいする議会統制の強化」(p.102-103)であり、国債発行の禁止等ではないからです。
このことを示す一番の証拠は、GHQの憲法草案です。憲法のうち財政に関わる部分の冒頭の大原則的な条文は、GHQ草案では以下のようなものです。
租税を賦課し、金銭の借入れをなし、公金の支出を認め、並びに貨幣および紙幣を発行し、その価値を定める権限は、国会を通じて行使されるものとする。
この条文では、「国会を通じて行使」という文言のもとに、財政に関する「議会中心主義の強化」が大々的に表明されるとともに、「金銭の借入れをなし」と国債発行も認めているし、「貨幣および紙幣を発行し、その価値を定める」という通貨発行権も真正面から認めています。
ここで、貨幣(硬貨)のみならず紙幣まで含めていることは、あまり深い意味はないのかもしれませんが、興味深いです。これは貨幣についてしか通貨発行権を認めていない合衆国憲法を超えています。
GHQの憲法草案は以上のようなものであるのに、これに対応する最終的な日本国憲法の第八十三条は以下のようになってしまっているのです。
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
いずれにせよ、以上のことから、GHQが日本を弱体化するために緊縮財政の制度化を企図し、そのために財政法4条を制定させて国債発行を原則禁止したということは、さすがに言えないだろうことは納得いただけるものと思います。
財政法4条の失われた可能性—積極財政のための財政法4条
続いて、この『昭和財政史』から見えてくる、財政法4条の意外な側面を見ていきたいと思います。それは、いまでは緊縮財政の根本原因とされる財政法4条は実はもともとは積極財政を可能にするものとして「も」企図されていたということです。以下の叙述は、財政法4条の忘れられた可能性に光を当てるものです。
まず、GHQとの折衝前、大蔵省内での財政法の改正に関わる審議の第一回のとりまとめ(1946年6月)に注目すると、その内容を記録するメモには以下のように書かれています(p.117)。
今後の国民経済のあり方を考へ、財政の国民経済に対する役割を規定する等、国民経済と財政との関係は予算制度等の改正の基本的問題であるが此の問題については、別に併行して検討すること。
『昭和財政史』は1970年代に書かれたものですが、この点について著者は「財政と国民経済との関連にとくに深い関心が示され、財政の現代的展開に対応した制度改正の必要性が示されていることは、興味がもたれる点である」(p.118)とコメントしています。
しかし、第二回の審議では、時間的制約のためか、関心は具体的な法案の作成に傾斜していき、このような野心的な計画は後景に退きます。ただ、それでも、省内の資料が将来の研究課題としているものの筆頭として「景気の循環に対応して予算の調整を行なうこと」(p.121)を挙げています。
以上の二つの当時の大蔵省の資料からの引用からは、当時の大蔵省が財政の現代的展開として、国民経済や景気に対する財政の積極的な役割を認めようと意図していたことが分かります。不景気のときには積極的な財政支出を行い、好景気のときには財政を緊縮化させるという、いわゆるケインズ的な財政政策を財政法に書き込もうとしていたのです。
そして、それは確かに一方では「将来の研究課題」とされてしまったわけですが、この意図はそれでもやはり最終的に財政法に書き込まれていたのです。それが財政法4条の後半、「但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」なのです。
このことは財政法の立法に携わった石原周夫の口述資料から明らかになります(p.174-175)。やや長くなりますが、非常に読み甲斐のある部分ですので、『昭和財政史』が引用している部分すべてをここに再掲します。
[財政法第四条は]公共事業費、出資金、貸付金の財源以外には公債、借入金を出してはならないという規定であります。主計局のなかでこれを立案いたしますときにいろいろな議論をいたしたものの一つであつたわけでありますが、御承知のように一九三〇年代の後半におきまして、北欧スエーデンだとか、ノールウエーという国におきましては、複予算といいますか、ダブル・バジエツト、御承知のように中立貨幣論というような考え方がありまして、景気の消長というものを財政をもつて調節して行く。非常に好況のときには政府がどんどん金を吸い上げて、金をためておいて、不況なときにはたまつた金を出して行つて、不況を緩和する、こういう一つの貨幣政策、貨幣理論から来る財政政策の考え方があるわけですが、そういう複予算といいますか、ダブル・バジエツトというものがありまして、経常予算と資本支出との二つのものを置いて、資本支出を調整する。それを大きくしたり、小さくしたり、その財源を公債に求めたり、あるいは一般会計から繰入れたりするという形で、景気の消長を、政府の資本投資というものの動かし方で調節して行くという考え方、この考え方は積極面であります。この四条を入れましたときには、そういうような積極面から財政政策というものが、一つの景気政策的な動かし方をして行くのだという考え方に対しまして、もう一つは、当時も非常に強い議論であつたのでありますが、戦時中の公債政策というのはいかぬじやないか、この際、財政を通ずる根本の建て方をするときには、赤字公債を出さないということを明らかにしようじやないかというような両方の議論を取入れまして——これは今申上げたダブル・バジエツトのような積極的な意味における表現になつておりませんが、これは両方に動き得るということを考えまして、この条文がつくつてあるわけであります。この条文をつくりまして以後、インフレーシヨン、あるいはその後の安定経済という時期におきましては、まだこの条文のところまでは行つていないわけでありますが、ぼつぼつこの条文を活用するような議論が出かかつて来ているわけであります。(p.174-175)
これに対する『昭和財政史』執筆者のまとめが的確と思われるので引用します。
とくに注目しなければならないのは、立法者は、(…)戦争財政への反省という時代精神に強く影響されながらも、決してそれのみをかたくなに守ったわけではなく、他方では、現代における新しい公債政策の展開に対しても決して無関心ではなかったことは、当年の予算改革の動向にも注意を払い、スウェーデンの事例についても研究していたという点である。第四条は、このように、一方では、戦争財政への反省からくる健全財政への志向、他方では当年における公債政策の新展開への配慮という二つの観点を組み合わせながらも、前者に重心をかけた内容として立法化されたものといえよう。(p.175-176)
歴史を掘り起こしてみることは面白いですね。財政法4条のGHQ陰謀論を検証してみようと思ったら、期せずして財政法4条に盛り込まれていた進歩的な意図を見出すことになりました。
それだけに、財政法4条に盛り込まれた資本投資・資本支出、要するに日本でいう建設国債の方まで含めて国債発行を無くしてしまおうというプライマリーバランス黒字化目標における、財政についての考え方の異様な退化が際立ってきます。
積極グマと暗渠づたいおじさんの余談①—財政法4条とPB黒字化



財政法4条に対して、プライマリーバランス(PB)黒字化目標が退化しているって、どういうこと?



うん、これをしっかり理解するためには、まず財政法4条が禁じているのは通称「赤字国債」だけだということを正確に把握しないといけない。
積極財政を可能にするものとしての財政法4条ということで論じたけど、財政法4条は「公共事業費」などについては国債発行を認めていたよね。これはなんでかというと、まさに石原周夫が語っていたように、経常予算とは別枠で資本支出の予算を用意しておいて、この資本支出の方で景気対策を行う建て付けになっていて、こちらは景気対策として不景気で税収が減っているときにこそ支出しなければならないから、国債発行、いわゆる「借金」でしてもいいというか、むしろそうしなければならないからだ。また、資本支出という言い方は、別の含意もあって、支出に見合う収入が見込めるとか、支出に見合う資産が残るから「借金」で賄ってもいいというニュアンスもある。で、この財政法4条但し書きで認められているのが、景気対策で使われ、資産が残る「建設国債」というわけ。それに対して、この財政法4条の但し書きで正当化できない国債が、建設的な投資に使われるわけでもなく、資産も残らない、単なる赤字の穴埋めだという意味で、慣例的に「赤字国債」と呼ばれているよ。正式名称は特例国債で、特例公債法というのを毎年(最近は五年ごとに)通すことで正当化されているんだ。以上を踏まえて、財政法4条は赤字国債を禁じたと整理されることもある。
で、プライマリーバランスへの退化だけど、要するに財政法4条は投資的な経費は別腹だよといって建設国債はしっかり認めているのに、プライマリーバランス黒字化は、政策的経費はすべて、つまり、国債の利払い以外の支出はすべて税金で賄え!ということだから、いわゆる赤字国債だけじゃなくって、建設国債まで事実上、否定しているんだよ。それはいわば、但し書きなしの財政法4条みたいな存在なんだ。
これによって、ここ20年間、公共事業が抑制されてきたし、インフラは劣化し、建設工事の供給能力も縮小してきてしまった。よく言われることかもしれないけど、小泉純一郎と竹中平蔵の残した最大の負の遺産と言っていいだろうね。
積極グマと暗渠づたいおじさんの余談②—財政法4条は廃止・改正すべきなのか



ふむふむ、で財政法4条って廃止したり改正したりした方がいいと思う?
積極財政派の僕としてはやっぱり一番好きな国会議員の一人である西田昌司は、財政法4条と憲法9条を一体と見て、これこそ日本を弱小国にしようとGHQが押し付けた戦後レジームの本体なのだから、財政法4条は憲法9条と同様に改正すべきだと主張しているね。西田さん曰く、「財政法4条=戦後レジーム」という議論を、最後はなんとか安倍晋三にも納得させることができて、安倍さんも参院選が終わったら改正に動こうとしてたらしいよね。2022年の安倍さんが殺された参院選。



安倍さんはコロナ禍で退陣した後は、MMTを一定踏まえた完全な積極財政派として覚醒しつつあっただけに、あの事件は残念だったね。日本の積極財政への転換を数年は遅らせることになったと思う。それは致命的な数年かもしれない。
僕もいまでもたびたび安倍さんの事件直後の藤井聡と西田昌司の対談動画(1)(2)や藤井聡のラジオなんかを聞くよ。後者は冒頭で「安倍晋三は消費増税と緊縮財政で日本を破壊した最悪の政治家だ」と徹底糾弾するお便りが紹介されて、それがなんか妙に、この言葉が適切かはわからないけれど、感動的なんだよね…。
で、財政法4条だけど、僕も基本的には改正に賛成かな。ただ、この記事の本文から分かる通り、それはそれが日本を弱体化するGHQの陰謀であり戦後レジームの本丸だからというわけではない。むしろ、財政法4条自体は当時としてはとても先進的なものだった。もちろん、長期では不況期の赤字を好況期の黒字で埋める形での財政均衡を目指しているから、現代の視点からは不十分であるにしても、そんなに悪いものではなかった。プライマリーバランスの黒字化目標に比べれば何百倍もマシな代物。だから、まずは法律ではなく閣議決定に過ぎないPB黒字化目標の撤廃が先で、財政法4条はそのあとじっくり考えればいい。
それでもどちらかといえば財政法4条も改正すべきだというのは、いわゆる赤字国債の発行も恒常化していて、財政法4条の建設国債だけ認めるというのはもはや現実的ではないと思うから。そして、現代の豊かな社会では財政赤字が原則となると思うから。だから、財政法4条の国債発行禁止規定は赤字国債を許し、特例公債法を不要にする仕方で改正されるべきだとは思う。そのうえで財政法4条のダブル・バジェットじゃないけれど、どのような配分で税財源と国債財源のバランスを考えるか、もちろん、税は財源ではないにしても、実際には税は徴収するわけで、それと支出との関係をどう構想するかは、僕にとってもこれからの課題だな。



積極財政派が認める金融機関系のエコノミストといえば、MMT紹介者の島倉原、一貫して積極財政的な永濱利廣、60年償還ルールの欺瞞を暴いて財務省のプロパガンダ・ワニを退治した会田卓司くらいだと思うんだけど、その会田さんは、アメリカの制度を参考にしてなのか、義務的支出には税財源を充てて、義務的ではない裁量的支出には税財源を充てないという仕方で、一種のダブル・バジェットを考えてるみたいだね、そう言った話も参考になるかもしれない。
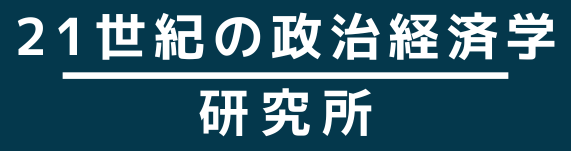
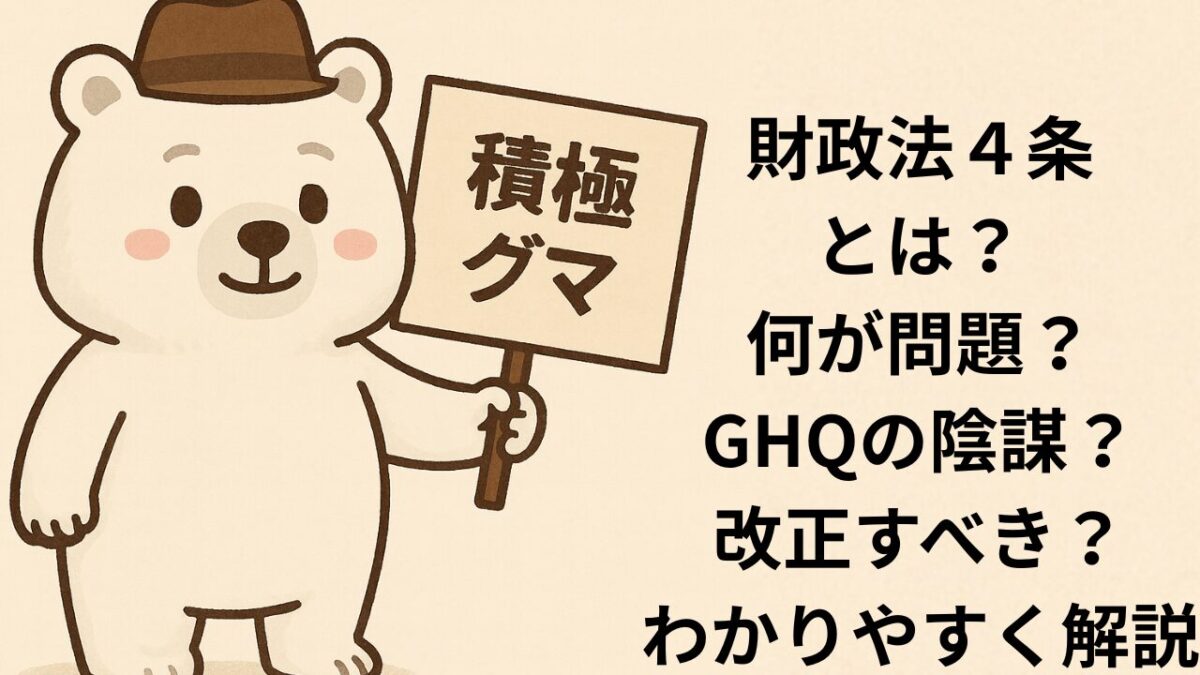
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます