この記事は約21分で読めます。
時間のない方はこちらの3分要約版をご覧ください。
この記事では、大阪大学で教鞭をとった小野善康のいわゆる小野理論を、私なりに要約的に解説します。
私の理解では、現代社会は「ゆたかな社会」であり、生産の過剰、つまりは供給に対する需要の不足によって特徴づけられます。ここで「需要」には家計が財やサービスを買う「消費」と、企業が自分が売る財やサービスを作る準備として財やサービスを買う「投資」があります。
したがって、需要が不足するとは、「消費」か「投資」、あるいはその両方が不足することです。小野理論は、このうち「消費」の不足を説明する理論です。「投資」の不足を説明するものとして、リチャード・クーの理論があります(こちらの記事参照)。
私としては、小野理論とクー理論を総合することで、現代の経済の需要不足についてもっとも的確なスケッチを得ることができると思っています。
今回は、この小野理論について、それを「消費社会から「貯蓄=投資(投機)」社会へ」というより広範な社会的文脈のなかに置くことで、理解を深めたいと思います。
 積極グマ
積極グマ小野理論って、僕は最もしっくりくるマクロ経済学だと思ってる。積極財政を正当化するには、需要不足が起きていることが基本的な前提の一つだから、小野理論は学んでおいて損はないね。



そうそう、なんか実感にあうんだよね。もっと積極財政界隈で評価されてもいいと思う。平成から受け継ぐべきものがあるとすれば、それは小野理論だよ。
社会変化のアウトライン―生産社会・消費社会・貯蓄社会
1970年ごろを画期として「生産社会」から「消費社会」への転換が生じたということが、かつてよく語られました。いわゆる消費社会論です。
その後、社会はどうなったのでしょう。1990年ごろから「消費社会」は「貯蓄社会」に変化したのではないでしょうか。そんな見通しをまずは大雑把に語ってみたいのです。
生産と消費が対義語であるのと同様に、経済学においては、消費と貯蓄も、家計の所得の二つの利用先として、対義語となっています。家計はお金を得たら、それを消費に使うこともできるし、貯蓄として貯めておくこともできるのです。
私の考えはこうです。「生産」社会は、第一の対義語の対の反対側である「消費」社会に転換し、「消費」社会はいわば流産して第二の対の反対側である「貯蓄」社会に転換した。そんなふうに考えてみたいのです。
そして、この貯蓄社会は「貯蓄=投資(投機)」社会です。というのも、「貯蓄から投資へ」という日本政府のスローガンの与える印象に反して、マクロ経済的に見れば、個人が行う(主に株式への)金融的な投資(投機)は実物的な需要を生まないという点で貯蓄と等しく、企業が行う実物的な投資とは似ても似つかない代物だからです。この区別のために、この記事では「金融的な投資」を「投機」ないし「投資(投機)」と表記します。
企業が行う投資では、お金はたとえば工場を建てるための財やサービスの購入に支払われますが、個人が行う金融投資では、お金は基本的に株式の中古転売に使われ、金融市場の中を行ったり来たりするだけなのです。
さて、このような消費社会から「貯蓄=投資(投機)」社会への転換を語るにあたって、非常に有用なのが「小野理論」です。それこそがまさに貯蓄社会の経済理論だからです。
生産社会から消費社会へ―高度経済成長とその終わり
まず、1970年ごろの生産社会から消費社会への転換を見ていきましょう。
それまでは生産側、つまり、「作り手=売り手」が社会を主導していました。戦後の世界では、いま先進国と呼ばれる国々で、家電や自動車といった耐久消費財の大量生産が行われ、それらは文句なしの便利さによって、飛ぶように売れていきました。
その大量生産システムが、生産性を大幅に向上させ、それが労働者の賃金を大きく上昇させることによって、各種の耐久消費財が労働者を含む一般の家庭に急速に浸透し、生活に革命を起こしていったのです。いわゆる戦後の高度経済成長です。
この生産社会では「需要」は自明であり、それに「供給」が追いつくかが問題でした。消費は旺盛で、生産がそれに追いつくかどうかが問題だったのです。希少性の時代でした。そこでは生産こそが最も重要であり、それが社会を主導する原理となります。
1970年ごろは、この高度経済成長が耐久消費財がある程度まで普及し切ったことで終わりを迎えた時期にあたります。一つの時代が終わったのです。
飛ぶように売れる商品がもはやないとすれば、社会を主導するのは「生産」ではなく、「生産」の反対語である「消費」の側です。「消費社会」の誕生です。そこでは、需要はもはや自明ではなく、供給側は需要を創出することを考えなければならなくなりました。商品がデザイン的に一気に多様化し、広告が際立って重要になったのも、この時代です。
消費社会論からすれば、もはや真面目にコツコツ働く労働者が社会を主導する存在なのではありません。経済の制約は生産・供給ではなく、消費・需要にこそあるからです。社会を主導するのは次々に目先を変える消費者であり、そんな人々を幻惑するべく、さまざまな記号やイメージをまとう種々雑多な商品が生み出されていくことになるのです。この幻惑だけが経済を前に進めることができるというわけです。
消費社会から貯蓄社会へ―バブルから失われた30年へ
しかし、消費者が千変万化の商品に幻惑され踊り続ける、この楽しげな消費社会のイメージ、すなわち、消費社会論は、今から振り返れば、80年代の幻だったと言わざるを得ません。
私の印象では、消費社会論は他ならぬ日本でこそ大いに流行したように思われるのですが、それはその論のうわついた雰囲気そのものが、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われ、バブルの熱に浮かれた80年代の日本の空気に支えられたものだったからでしょう。
そんな多幸感に満ちた80年代が終わり、バブルがその名の通りに泡と消えると、陰鬱な世紀末、いわゆる「失われた30年」の始まりとなる90年代が始まります。
その90年代の始まりとともに、消費社会の流産が決定的となり、「貯蓄=投資(投機)」社会が誕生します。
この貯蓄社会の経済理論と呼ぶべきなのが、日本発の経済理論、小野善康の小野理論です。それは「失われた30年」が落とし子とでもいうべきものです。
今回は『不況のメカニズム』『資本主義の方程式』の2冊に基づいて、簡単にその概要を説明したいと思います。
ケインズ革命の栄光と挫折―小野理論の前史として
この小野理論は、ケインズの再解釈に端を発する理論です。そのポイントは新古典派経済学によるケインズ経済学の総合を乗り越えることにあります。一歩一歩、話を進めていきましょう。
ケインズは経済活動のレベルを決定するのは「供給」ではなく「需要」だとする「有効需要の原理」を提唱しました。それにより、「供給が需要を生み出す」という「セイ法則」を奉じつつ、経済活動のレベルを決定するのは「供給」だとする(新)古典派経済学を批判したのです。
ケインズ経済学は、需要が足りなくて経済活動の足が引っ張られると考えるのに対して、主流派経済学は、供給が足りなくてそうなると考えるのです。ケインズ経済学は物が溢れて売れ残る「豊富」の時代の経済学なのに対し、主流派経済学はそもそも物が足りない「欠乏」の時代の経済学だとも言えるでしょう。
さて、このように真っ向から対立する両者ですが、ケインズの死後にケインズの経済学は「新古典派総合」という形で新古典派経済学、つまり、主流派経済学に「総合」されてしまいました。
この総合はいかにして可能になったのでしょうか。それはケインズの「有効需要の原理」を「短期」に押し込めることによってでした。
そもそも主流派経済学からすれば、市場とは価格が変化することで需要と供給を一致させるメカニズムです。需要が足りないならば、需要と供給が等しくなるまで価格が下がるだけの話なのであって、実際に物を作る資源や技術や人材が足りないために生じる供給の制約の方が重大な問題なのです。
そういうわけなので、ケインズがいうような需要不足は価格の調整メカニズムが完全に働くまでの「短期」の問題で、その解決策は、市場に対する規制を撤廃して、すばやく市場の調整メカニズムが働くようにすることでした。
一例を挙げると、最低賃金をなくして労働者の価格がどんどん下がるようにすれば、労働者の供給過剰としての失業はなくなるという論理です。その場合、企業はどんどん労働者を雇いたくなるし、労働者はどんどん働きたくなくなるわけなので、労働者の需要が増え、供給が減って、両者が一致するようになるのです。
こういうわけで、「新古典派総合」によれば、需要不足は短期の問題であり、中長期における真の問題は供給制約です。そして、市場メカニズムを円滑に働かせることで、この「短期」は短くすることができるというのです。
小野理論は、このように「総合」されてしまったことにはケインズ自身にも責任があると考えます。ケインズ自身が需要不足が生じる論理を完全に明確にはできず、需要不足の原因がつまるところ価格調整が機能しないことにあるかのような解釈を許してしまったというのです。
小野の整理によれば、ケインズの需要不足の論理は以下のようなものです。まずケインズは所得の特定の割合のみが消費に回るという「消費関数」を前提とします。そのうえで所得のうち消費されなかった分、すなわち、貯蓄と等しいだけの投資が生まれない理由を、「流動性選好」に求めます。それによって、金利の高止まりが生じて、貯蓄と等しいだけの投資が生まれないのだというのです。
これはどういうことでしょうか。主流派の経済学の考えをまず理解しましょう。
生産が行われると、その生産の費用として、地主には地代が、労働者には賃金が、資本家には利潤分が支払われることになります。人々はこうして所得を得るわけですが、この所得が全部支出され消費に回るなら、生産されたものが基本的に全て買われるでしょう。というのも、一方で生産物の価格は先の費用の総計で、他方で、その費用の総計と同じだけ、人々は所得を得ているからです。
しかし、人々は所得を全て消費に回すとは限りません。その時には貯蓄が生まれ、その反対側で生産物の売れ残りが生じます。
しかし、ここで売れ残りは生じないというのが主流派経済学の論理です。人々の貯蓄と同じだけの企業による投資が生まれるからです。
どうしてでしょうか。一歩づつ、その思考の流れを追っていきましょう。
まず、人々が貯蓄をするといっても、タンス貯金では金利もつかないので、人々はお金を銀行に預金したり債権を買ったりします。これらのお金は企業に投資資金として貸し出されるわけです。このときのお金のレンタル料が金利です。
さて、もし、企業の資金需要より、人々の貯蓄による資金供給の方が大きければ、お金の値段としての金利が下がります。そうすれば、企業はコストが下がって収益を見込める事業投資案件が増えるので、そのぶん資金需要が増加します。他方で、人々は金利という貯蓄のうま味が減るので、貯蓄を減らして消費を増やします。この金利下落が貯蓄と投資が等しくなるまで続くのです。
要するに金利という価格の調整メカニズムによって、資金の供給としての貯蓄と資金の需要としての投資は等しくなるというわけです。こうして、人々の所得は人々自身の消費と(貯蓄を経由した)企業の投資によって、すべて有効な需要となり、結果として、売れ残りは生じません。これが主流派経済学の論理です。
これに対してケインズは、「流動性選好」を持ち出します。「流動性」とは、本来は取引を通じてすぐに別のものに代えられるという性質のことですが、この文脈では主にもっとも流動性が高い「現金」のことを指します。人々は、さまざまな動機で現金を手元に置いておきたいと思います。
ケインズが想定した主要な理由は、金利がある一定の値まで下がると、それ以上は下がる余地は少なく、むしろ上がる余地が大きいと思われるようになることです。債権の金利と価格は逆に動くので、これは債権価格について上昇余地より下落余地が大きいことを意味し、人々が債権を買いたくなくなるのです。このため債権の価格は上がりきらない、ということは、金利は下がりきらないのです。こういった流動性選好のため、貯蓄の全てが債券や銀行預金その他の収益資産になるわけではなく、したがって、投資のための資金として供給されるわけではありません。
こういうわけで、金利は高止まりして投資が増えません。こうして、貯蓄>投資となって、需要不足が生じるのです。
しかし、以上のケインズの論理に主流派経済学は反論できます。そもそも、ケインズは消費関数の前提によって、所得によって消費がその一定割合として自動的に決定されるとしていますが、これは物価下落の効果を見落としているというわけです。需要不足ならば物価が下落するはずであり、これが人々の手持ちのお金の残高を実質的に増やすことになる。そして、この実質残高効果で消費が上向くはずだというのです。
さらに、この実質残高効果は貯蓄にも適用されます。流動性選好に関しても、現金一単位の実質価値が増えるのだから、物価の下落とともに手持ちの現金を持ちたいという流動性選好も弱まって、家計の余剰資金は銀行や債権に向かい、それによる金利低下もあって、結局、そのお金は投資に回ることになるだろうというわけです。
だから、結局、ケインズのいう需要不足が続くとすれば価格調整メカニズムの機能不全のせいなのだ、というわけです。
小野理論によるケインズ経済学の再構成
小野理論とは、この新古典派の価格調整メカニズムによる反論に耐えうる形でケインズの着想を再構成しようとした理論です。そのポイントは価格調整の機能不全とは関係ない形で需要不足の存在を示すことにあります。
具体的には、その再構成の試みは、(1)「流動性選好」の概念を、単に金利を高止まりさせて投資を抑制するものとするのではなく、消費をも制約するものとして全面化しつつ練り直すこと、(2)新古典派経済学が通用する「成長経済」の時代と、ケインズ経済学(=小野理論)が妥当となる「成熟経済」を区別することによって、遂行されます。
その基本的な着想を私なりに説明すれば以下のようになります。
成長経済の論理―生産社会の経済成長
高度経済成長以前のような、まずは衣食住を満たすことが課題だった時代、あるいは高度経済成長期のような、圧倒的に便利な耐久消費財の普及期であれば、人々の消費意欲は高いです。
所得は基本的に消費に回すし、貯蓄をするにしても、それは将来の消費を見込んでのことです。人々が貯蓄をするということは、その分、生産物のうちに消費されない部分があるということで、そこが企業による投資を受け入れる供給力の余力となります。この余力が全て活用されない場合には、需要が不足することになりますが、将来には必ず消費が期待できる以上、企業は利潤を求めて躍起になって投資をするでしょう。こうして、消費と投資の需要で供給力の全てがカバーされることになります。
これが成長経済の論理です。
この時代には貯蓄が奨励されます。というのも、人々が消費をせずに貯蓄をすることで、供給能力の全てが、まだ足りていない供給能力の成長につながらない消費によって使い尽くされるのではなく、さらなる供給能力、すなわち、成長を生み出すための企業の投資に使われることになるからです。
わかりやすさのために農業にたとえるならば、収穫したお米を全て消費してしまったら何も残りませんが、その一部、それも昨年よりも多い量を消費せずに貯蓄しておけば、次の年には今年よりももっと多くのお米を収穫できるという話です。それを繰り返すことでお米の生産量は増大していきます。これが経済成長です。
成熟経済の論理―消費社会の流産と貯蓄社会の誕生
しかし、一通りの衣食住が満たされ、耐久消費財による近代的で便利な生活が実現してしまうと話は変わってきます。
消費の切迫感や、消費への激しい意欲は削がれ、基本的な満足感の中で、消費の効用は消費をすればするだけ下がっていきます。これ以上、消費をしてもなぁ、という気持ちになってくるのです。1980年代後半の有名な広告キャッチコピーにある通り、「ほしいものが、ほしいわ」というわけです。
他方で、ここがポイントなのですが、小野理論の、こちらもかなりの程度は妥当と思われる想定によれば、お金に関しては、確かにお金を持てば持つほど、もっとお金を持ちたいという欲望は減退していくものの、その減退の度合いは消費よりも小さいとされます。その減退には下限があるというのです。消費はもういいやとなるのに対して、お金はあればあるだけ悪い気はしないのです。
要するに、現代人の多くは、現在の消費水準を超えてさらに消費をするよりも、自分の銀行口座や証券口座の残高が増える方が嬉しいのです。口座残高が増えて「にんまり」する。その「にんまり」の効用の方が、追加的な消費の効用よりも大きいのです。
成長経済が実際に成長して豊かになるにつれ、人々の消費水準も資産水準も上がっていきます。それとともに、消費の欲望も資産への欲望も減退していくものの、前者が直線的に減退していくのに対して、後者の減退は徐々に緩やかになっていき、ある下限より下にはいきません。
すると、資産への欲望が消費の欲望に対して恒常的に優位に立つという段階がやってきます。それが要するに「成熟経済」です。
つまりはこういうことです。人々は所得を得たとき、それを消費に回すか貯蓄に回すかを選択するわけですが、消費の欲望は飽和して下がっているのに対して、貯蓄の欲望は下がり切ってはいません。すると、この両者への配分は、かなり貯蓄優位なところで決着します。所得のうちで消費に回す割合、消費性向が以前よりも下がっているのです。
それゆえに、成熟経済は、「消費社会」ではなく、「貯蓄社会」なのです。
とすれば、この所得のうちで消費に回らない貯蓄部分に相当する需要を、企業の投資活動が創出しなければいけません。さもなければ、供給能力の無駄遣い、要するに失業が発生してくるのです。しかるに、この貯蓄は、成長経済のときと違い将来の消費を見込んだ貯蓄ではないため、企業も将来の売上を見込んで投資をすることができません。結果として、総需要の不足、供給能力の無駄遣いが発生してくることになります。
こうして生じるのが慢性的な総需要の不足で、その帰結は物が売れずに物価が下がるデフレ傾向です。他方で、この消費の減退の裏面には貯蓄の蓄積があり、それがお金のだぶつきにつながって金利が低下していくなかで、余剰のお金は土地や株といった資産に流れ込みがちとなります。それは、そういった資産価格の異様な値上がり、すなわち、バブルを生み出す傾向に通じます。
この点でも、1980年代後半は示唆的です。一方では、先に触れた「ほしいものが、ほしいわ」と言われるような消費意欲の減退が意識される中で、土地と株の両資産がバブル的な騰起を演じました。時代は異様な好景気に湧いきましたが、その実、消費者物価は落ち着いていました。
資産バブルと物価のデフレ傾向の共存。1980年代後半は、成熟経済時代の始まりにおいて、その時代の根本傾向を予示していたようなのです。
「成熟経済=貯蓄社会」の帰結―経済成長の停滞と格差の拡大
さて、この成熟経済の時代の帰結を見ていきましょう。
まず、総需要の不足により経済成長は停滞します。
そもそも、先に確認したように、小野理論は、ケインズのいう「流動性選好」を全面化することで、もっとお金を持ちたいという人々の欲望が消費の欲望を上回る時代において、総需要不足が発生し、それが経済成長の足枷となるという事態が、価格メカニズムの機能不全とは関係なしに生じることを論じるものでした。
もう一つ生じるのが格差拡大です。
需要不足のなかでは供給力の過剰、すなわち、労働力の過剰が生じ、デフレの中で失業と低賃金労働が常態化します。普通の人々は、このように賃金が低く抑えられるなかで、生活のために多くを消費に回さなければならず、十分な貯蓄、資産の蓄積ができません。
他方のお金持ちはといえば、もう消費は満ち足りているので、所得の多くを貯蓄に回すことができます。それを単に銀行預金に積み上げていくだけでも資産が増えていくわけですが、実際にはそれ以上です。というのも、そのお金のかなりの部分は株や土地といった資産に流れ込み、それによって資産価格が継続的に上昇、お金持ちはよりお金持ちになっていくからです。
「成熟経済=貯蓄社会」の経済政策―何が「失われた30年」を生み出したのか
ここで政策的に重要なことは、消費に対する貯蓄の優位を少しでも反転させていくことです。
そのために重要なのは、貯蓄を不利にし消費を有利にするために、消費の先送りが損となるようにインフレ率を上昇させること。また、(小野自身はここまで言っていないとは思いますが)貯蓄をしてもあまりうま味がないように資産価格の上昇を抑えることです。
必要なのは、強制的に需要を生み出し、またインフレ率を上昇させる積極財政政策であり、需要の増大とインフレ率上昇には必ずしも寄与せず、資産価格を無闇に上昇させる金融緩和政策ではないのです。
また、より抜本的には、需要を生まないお金に税を課し、需要を生むお金に税を課さないことです。資産増税、資産取引増税、消費減税、企業の実物投資減税です。
これは要するにお金持ちからお金がない人たちへの再分配でもあるわけですが、お金持ちへの増税に対してよくある批判を回避できるという利点があります。お金持ちへの増税は、お金を稼ぐモチベーションを削ぎ、経済を停滞させると言われますが、ここで増税の対象となるのは主に資産からの所得、つまり、現にいま社会に貢献していることから生じるのではない所得だからです。
以上の観点からみると、やはりこの30年間は「失われた30年」を作り出すに足る失策の連続だったことがわかります。
まず、90年代から00年代に関しては、公的資金の注入による銀行のバランスシートの改善という根本的なバブル崩壊の後始末を先延ばしし続けているうちに、財政政策や金融政策といったマクロ経済政策への信頼が失われ、最終的に小泉政権で構造改革という供給強化のデフレ政策が採用されるという狂気じみた事態が生じてしまいます。インフレ率を高めて貯蓄に対して消費を有利することが重要だったのにも関わらずです。
そして、これを反省した第二次安倍政権にしても、結局は財務省と財政規律の制約により、財政政策は緊縮気味に推移し、政策は金融緩和の一本槍に終始します。それによって株価は上昇したものの、結局それは(金融的投資という)貯蓄を消費より優位にしたにすぎず、成熟経済、すなわち、貯蓄社会の根本問題を深刻にするばかりだったのです。
最後に、この失われた30年は、需要を生むお金の最たるものとしての消費にかかる消費税の増税の歴史でした。この失われた30年の間に、それは0%から10%まで段階的に上昇してきたのです。
貯蓄社会から「貯蓄=投機」社会へ
最後に、第二次安倍政権以降の政策に関して、私の意見として言っておきたいことがあります。貯蓄社会は、これまでも論じてきたとおり、そもそもが資産価格が上昇し続ける、非実物的-金融的な投資が優位の投資社会でもあるのですが、その側面が、第二次安倍政権以降に全面化することになったのです。アベノミクスは「貯蓄=投機」社会を完成させたのです。
それは、貯蓄社会についてのここまでの議論に登場した、お金持ちとお金がない人の中間の人々に関わる話ということもできます。
成熟経済、すなわち、貯蓄社会において、消費意欲より貯蓄意欲が上回るお金持ちは、貯蓄を重ね、資産価格の上昇にも助けられて、よりお金持ちになっていきます。他方で、まだまだ消費が足りずに消費意欲が高いお金がない人は、デフレ的な状況下で賃金が低くとどめられていることもあり、資産を築くことができません。
では、その中間の人々はどうでしょうか。こういった人々は、直近の消費に関して、飽和はしてないにしても、さしあたり不満はありません。直近の消費がギリギリだというほど、お金がないわけではないのです。他方で、将来には不安があります。だから、こういった人々はその不安のために、さらなる消費よりも貯蓄を選ぶでしょう。日本的な成熟経済の中間層は、不安から貯蓄に駆り立てられ、それなりの資産を築く人々です。
先ほどの繰り返しになりますが、成熟経済における経済停滞と格差拡大を反転するためには、消費と貯蓄の力関係の偏りを反転させる必要があります。そのために必要なのは、消費を有利にするための、インフレ率の上昇と、貯蓄を不利にするための、資産価格上昇の抑制です。それが実現できるのは、強制的に需要を発生させ、またそれによりインフレ率を高める積極財政政策であり、資産価格を無闇の上昇させる金融緩和政策ではありません。
そして、アベノミクスは、実際のところ金融緩和政策一本槍となり、資産価格を上昇させつつ消費税を増税することで、消費よりも貯蓄を圧倒的に有利にしてしまいました。「貯蓄から投資へ」という誤解を生むスローガンとは裏腹に、ここで言われているような金融的な投資は、基本的に金融資産を取引する人々の間でお金が行き来しているだけであり、実体経済に需要を生み出し、将来の供給力を生み出す、企業の「投資」とは似ても似つかないのです。それは需要を生まない点で、貯蓄の一形態にすぎません。
この貯蓄の優位性の確立の先に、またそれを確固たるものとするために現れたのがNISAという政策です。
この少額の投資に関しては利益を非課税とする政策は、金融緩和しかできずに結局のところ株価を上げることしか出来なかった安倍政権が、その自分の唯一の誇れる成果を先にのべた中間層にまで広げようとした政策であると位置付けられるでしょう。
これはなぜよくないのでしょうか。
第一に、これは本来進むべき方向とは逆に、減税によって貯蓄(=金融的投資)の収益率を高める政策であり、金融的投資の性質上、それでみんなが投資に殺到すれば、資産価格の値上がりによって、「貯蓄=投資(投機)」の収益率がいや増しに増す、そういう結果を生む政策なのです。もちろん、それ自体は悪くないにしても、この収益率の上昇は消費より投資だ!と消費を減らす効果があります。
第二に、これは中間層の(実際の生活ではなく)目線だけをお金持ちに合わせる政策です。貯蓄社会の弊害を緩和することは、要するにお金持ちからお金がなく消費性向が高い人への再分配によってしか可能でないし、また必然的にそのような再分配を結果することになります。
だから、それを実現するには中間層以下の多数派の力を結集し、少数の富裕層の政治的影響力を凌駕する必要があるのですが、NISAはこのうちの中間層、つまり、いくらか貯蓄する余裕がある人々の目線を富裕層の側に合わせる効果があるのです。
よく知られているように、日本では所得が一億円を超えると実際の所得税率が下がっていくという奇妙な現象が起きています。給与や事業等の所得は最高税率45%がかかるのに対して、株式からの所得には20%の一律税率しかかからないからです。必要なのは、異様に低く、富裕層に有利になっており、しかも労働や事業といった実際の社会への貢献と必ずしも結びついていない株式所得への課税の強化なのです。
しかるに、NISAがあることにより、このような増税が持ち出されると、それこそNISAの非課税枠に収まる程度の株式しかもっていないような中間層の人々が、「そんなことをしたら株価が上がらなくなる!」などと騒ぎ出すという事態が、実際に生じているのです。
要するにNISAは、中間層を株式投資に誘導することにより、彼らの視線(だけ)を富裕層と一体化させ、成熟経済ないし貯蓄社会の弊害を緩和する政策を不可能にする、そういう政策、今の不健全な経済体制を政治的に固定しかねない、そういう制度ともいえるわけです。
だから私は、NISAによって、貯蓄社会は、「貯蓄=投機」社会という形態へと最終的に進化したし、またその形態が政治的に固定される結果も生み出しつつあるのではないかと考えます。
必要なことは、むしろNISAを「NISAの枠があるから普通の人たちには増税にならない」というエクスキューズとして用いることで、金融資産課税の正当化根拠とすることでしょう。
金融市場でお金がぐるぐる回って資産価格がどんどん上昇していくことではなく、お金が実物的な財やサービスへの企業の投資や家計の消費に向かい、そこをお金がぐるぐる回ることで、生産と消費が活発化していくこと、それこそが多くの人が仕事で活躍の場を得られたり、また多くの人が財やサービスの便益を享受できたりということで、経済的に豊かな社会を可能にするものだからです。
積極グマと暗渠づたいおじさんの余談



あれ、最後の二つの項目、政策的な部分と「貯蓄=投機」社会の部分は、小野理論の主張なのか、おじさんの主張なのかが少し曖昧な感じがするな。



あー、ちょっとそこ曖昧になっちゃってるね。また今度、別の記事で、そこはしっかり峻別して論じたいと思う。小野さんの本をいままた以前よりも広範に読んでいるところだから。いまのところは、ちょっと僕による「敷衍」という部分があることに注意ということで…。
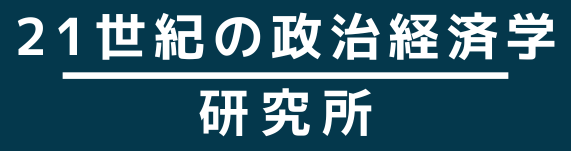
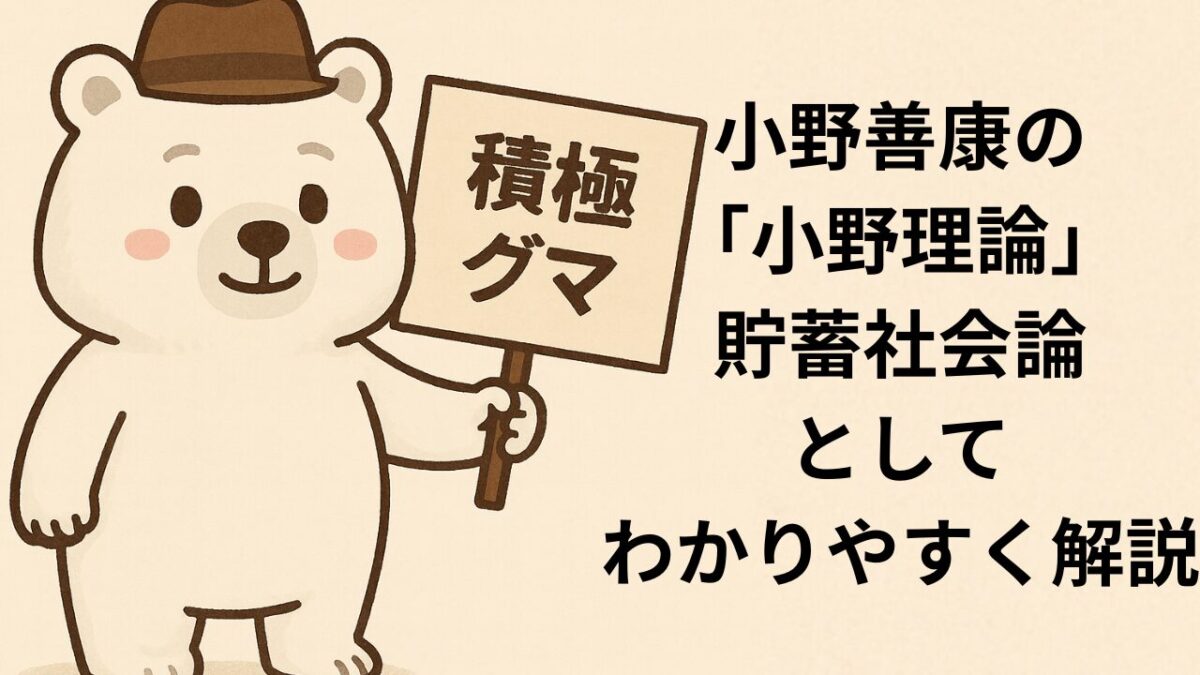
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます