この記事は約7分で読めます。
時間のない方はこちらの3分要約版をご覧ください。
この記事は、2025年(原書は2023年)に翻訳出版された貨幣論の本、ポール・シェアード『パワー・オブ・マネー 新・貨幣入門』の部分要約的な書評です。
私なりにこの本を一言でいえば「ステルスMMT本」であり、その中で私にとって印象的なメッセージ(の一つ)はいわば「Don’t Tax the Rich」とでもいうべきものです。
前者の「ステルスMMT本」という点については、それもそのはずで、著者のポール・シェアードはMMTの本拠地レヴィ経済研究所のアドバイザーに(スティグリッツやマッツカートと並んで)名を連ねています。
後者の「Don’t Tax the Rich」ついては、MMTの思考を徹底すれば、「Don’t Tax the Rich」、「富裕層は放っておけ」という結論が出てくるのではないかというのが非常に面白いところです。
順次見ていきましょう。
 MMTanuki
MMTanukiMMTの後で、どんな貨幣論が可能なんだろうと思ったら、ステルスMMTなんだね。



そうそう、僕もMMT以後の貨幣論を期待して手に取ってみたら、基本はただのMMTだったんだよ。もちろん、上で予告したような面白い部分もあるから、それについて詳しく紹介するね。
「ステルスMMT本」としての『パワー・オブ・マネー』
まずステルスというのは、本文中では、MMTは数度しか出てこず、自分はMMTだと名乗ることも全くないにもかかわらず、基本に置かれている立場があからさまにMMTまんまであるという事態を指しています。MMTについてよく知らない方は、当サイトの以下の記事群をご覧ください。


流石に著者はそのことに自覚的なはずです。著者は戦略的に、ステルスというか、トロイの木馬というか、そういうやり方をとっていると見た方がよいのでしょう。MMTというとひどい偏見が蔓延しているので、その名を隠して語ることで、MMT的貨幣論をそれと気付かれないままに主流派に流し込んで、主流派を換骨奪胎してしまおうという戦略です。
MMT派からすると、それだけだとしょうもないということになりそうですが、本書は単にそれだけで終わってはいません。このトロイの木馬戦略は、単にMMTを焼き直すだけではなく、MMTを左派的なイデオロギーから脱色するような発展的な考察によって、MMTの根本部分を主流派に実際に受け入れやすくしている点もあり、そこは注目に値します。
それを一つ取り上げるとすれば、MMT的な思考を徹底すると「富裕層は放っておけ」、いわば「Don’t Tax the Rich」という結論が出てくることを論じている点です。MMTは日本では主に右派に広がっていますが、本来は米国の民主党の最左派周辺から出てきた左派的なものです。そして、左派といえば富裕層に厳しい。
しかし、本書はMMT的な思考を徹底することで、むしろ「富裕層は放っておけ」という結論に至ります。MMTが帯びる左派的なイデオロギーが脱色されているのです。
真にMMT的思考はなぜ「富裕層は放っておけ」と結論するのか
さて、なぜ、「富裕層は放っておけ」ということになるのでしょうか。これは本書の第五章で論じられています。その議論を、私なりに語り直してみましょう。
MMTの原則からすると、政府が支出をするのに、お金を税金として集める必要はありません。「税は財源ではない」。もちろん、借りる必要もありません。「国債は借金ではない」。ただ、通貨発行すればいいだけです(現在と同様の国債発行や日銀が国債を直接引き受ける明示的財政ファイナンスでも問題ありません)。では、真の意味での財源とは何でしょうか。それは余剰の実物的リソース(資源・インフラ・資本設備・労働力・技術・知識…)です。
この種の実物的な余剰がないのに政府が支出すれば、政府は民間から実物リソースを奪ってしまうことになります。逆に余剰があるなら、政府は通貨発行(等々)でもって、それを購入し、それで生み出される財やサービスを人々に提供しても、何かを民間から奪うことにはなりません。つまり、政府の力(で動員された人々の力)でもって人々が享受する財やサービスが純増します。
さて、ここで富裕層を考えます。普通は税が財源だと考えますから、お金をたくさん持っている富裕層から税をたくさん取ろうということになります。しかし、MMTにとっては税は財源ではありません。では、税の意味は?もちろん、MMTには税が貨幣を動かすといった議論もあるわけですが、今回はそれはいったん置いておいて、財源との関係の文脈でいえば、税の意味は、税金を取ることで民間の購買力を奪い、実物リソースを解放することです。
経済が完全雇用状態で、全ての実物的なリソースが使われている状態では、政府が何かをしようと思って支出をしても、実物的なリソースの奪い合いとなり、インフレを引き起こすだけです。そういう場合には、政府が何かをするためには、まず徴税によって民間の購買力を奪い、それによって実物リソースを解放しなければなりません。それが財源の文脈における税の意味なのです。税は、民間の購買力を奪って、実物リソースを解放することで、実物の余剰という政府の財源を生み出します。
すると、富裕層についてはどういうことになるでしょう。富裕層・超富裕層は、もちろん、普通の人よりも多くお金を使いますが、その差は、彼らが持つ資産と普通の人の資産との差ほどには、大きくありません。富裕層が普通の人の一千倍の資産を持っているとして、彼らの消費額は一千倍ではない。もしそうなら、そもそも彼らは富裕層であり続けられないでしょう。
だとすると、どういうことになるでしょうか。百億円持っている人から一億円徴収しても、そもそもその一億円は使われないものだった可能性が高いですし、それが取られたからといって、その人は消費生活を変更しないでしょう。ということは、この徴税によって解放される実物リソースはないはずです。
また、こういうことも言えます。左派に限らずある種の人たちは富裕層の莫大な富を嫌悪しますが、富裕層がただお金を貯めているだけである限りで、その富は私たち普通の人に被害を及ぼしません。だって、私たちが欲しいものを彼らが買い占めるわけではないからです。彼らが普通の人の生活に必要不可欠なものを買い占めるならば、確かに彼らは害悪です。しかし、彼らは米を何トンも買い占めて私たちを飢えさせたりしません。そんなに買っても食べられないのですから。
私たちは富裕層が絶対に使い切れないお金を溜め込むのを微笑ましく見ていれば良いのです。富裕層にはその莫大なお金、つまりは電子データとしての数字を貯めてもらって、気持ちよくなっていてもらいましょう。
現代の富裕層の(全てではないにしても)多くは、起業した会社の株式によって富裕層となっており、それは彼らが世界に新しい財やサービスを供給した結果です。それで得た資産を富裕層がそれほど使わないなら、富裕層は世界の財やサービスを増やしたのであり、過剰な消費によって減らしたのではないのです。そして大事なのは電子データに過ぎないお金ではなく、実物的な財やサービスです。だから、私たちにとって、富裕層は嫌悪すべき存在ではなく、むしろ愛すべき存在なのです。彼らは私たちから奪うのではなく、私たちに与えているのですから。
こんな具合です。
問題は富裕層のお金そのものではなく、その使い方である
このような議論をどう考えるべきでしょうか。問題は、彼らが溜め込んでいるお金をどう評価するかでしょう。確かに、このお金が今後も全然使われないのだとすれば、以上の議論は成り立ちますが、それがもし使われるとすると、前提が崩れてきます。富裕層が実物リソースを買い漁り、インフレが起きて普通の人々の生活が成り立たなくなるかもしれません。しかし、私たちの生活に本当に必要なものの多くは、買い占められるようなものではないことも事実でしょう。食べ物やガソリンを何万人分も買い占めてどうするのだ、という話です。
もし私たちの誰もが必要とするもので買い占められるものがあるとすれば、それは土地です。不動産のインフレが世界的に大いに問題になっているのは、私たち普通の人々が必要とするもので、富裕層がその財力で持って買い占められるもの、この両方を満たすものとして不動産があるからでしょう。その意味では、不動産投機の適切な規制は必要だと思われます。株が上がっても庶民には利益も損害もほとんどありませんが、不動産が上がるのは、すくなくとも不動産をまだ持っていない庶民からすれば、大迷惑です。
また、もう一つ別の問題は、その方が儲かるからという理由で、産業の富裕層シフトが起きてしまうことです。例えば、富裕層向けの宿泊施設の方が儲かるからと、人々がそちらの産業に移ってしまい、そのあおりを受けて、高齢者を介護する人々がいなくなり、高齢者が介護を受けられない、あるいは受けられるとしても富裕層向けのホテルと同じくらい高いというようなことになってしまうことです。これは問題です。
いずれにしても、問題は富裕層の資産そのものではありません。むしろ、その使い方を(必要であれば)制御することだけが重要なのです。それが、税は普通の意味では財源ではなく、それが財源であるとすれば、それによって実物リソースが解放されるからであるという真にMMT的な思考の帰結なのです。
【注:この本の著者シェアードは、富裕層のお金が可能にする富裕層の政治的影響力については、これを警戒しています。私はそれに富裕層はMMTに反対しない限りで無害であると付け加えたいと思います。】
以下のリンクで、この本の「はじめに」の部分を早川の公式が配信しています。
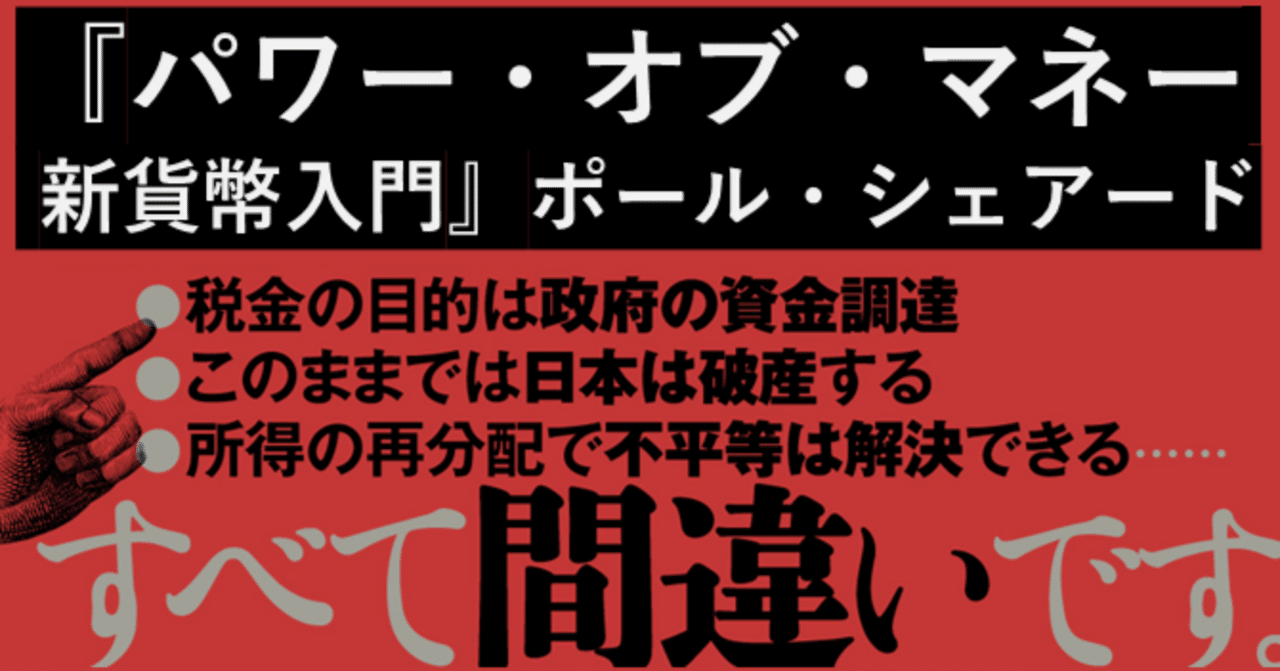
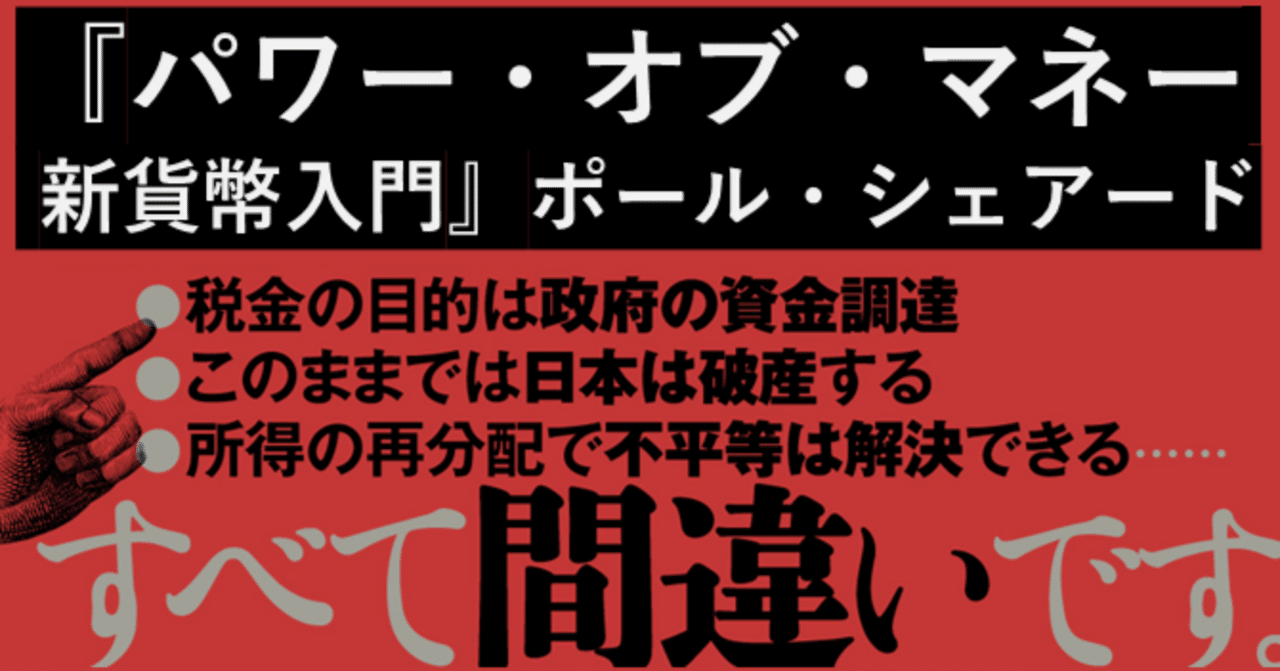
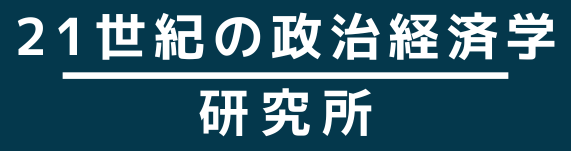


※コメントは最大500文字、5回まで送信できます