この記事は約17分で読めます。
この記事は中野剛志著『入門 シュンペーター』の読書録です。その書評的な要約を提供します。
時間のない方は以下の3分で読める簡単版記事をご覧ください。
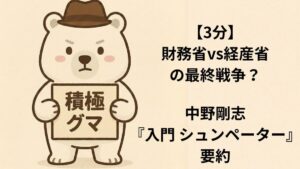
この記事の概要—経産省宣言とシュンペーターの奪還
前半部は書評的な部分で、本書を財務省と他の省庁、特に経産省との争いという文脈に位置付けます。本書を経産官僚でもある中野氏のいわば「経産省宣言」のようなものだと読むのです。それは平成の時代に、財務省の緊縮財政路線と主流派経済学の市場中心主義(新自由主義)が共鳴するなかで、他の各省の仕事が過小評価され、その予算が抑制されてきたことに対して、経産省の(反新自由主義的な一派の)側から放たれた反撃なのです。
後半部は要約的な部分で、本書の基本的な内容を要約します。それはシュンペーターをいわば「財務省の緊縮財政路線と主流派経済学の市場中心主義との共鳴」から取り返す作業です。私たちはシュンペーターのいわゆる「創造的破壊」「イノベーション」をなんとなくこの共鳴の文脈で解釈しています。小さな政府を実現し、競争を阻害する公金依存や岩盤規制、そういう意味での「既得権益」を排除すれば、市場の競争にさらされる中で、「イノベーション」が生み出されるというふうに。
中野氏はこのようなシュンペーター批判に異議を申し立て、むしろ、シュンペーターを国家の産業政策に親和的な存在として再解釈します。自らの産業政策肯定論的な立場へとシュンペーターを奪還しようとするのです。
諸省庁の争い―Der Streit der Ministerien
中野氏については、以前に「新しい京都学派」について論じた記事で簡単に触れたことがあります。そこで私は「新しい京都学派」の四天王のうちの一人として、一時京大にて准教授だった中野氏を挙げました。
さて、京都の積極財政派を「京都学派」という呼ぶこと自体や、上の記事を『インサイド財務省』の引用から始めた通り、財務省主計局の流儀です。再度引用しておきましょう。
新たな警戒対象として財務省が意識するグループもある。「京都学派」。京大教授で安倍ブレーンの内閣官房参与を務めた藤井聡と、京都選出の西田昌司自民党参院議員を、予算編成を担う主計局ではこう呼ぶ。『インサイド財務省』p.37
このことを前提として、本記事では、中野氏の『入門 シュンペーター』を読むにあたり、事態をカントの『諸学部の争い(Der Streit der Fakultäten)』をもじった「諸省庁の争い」という観点から眺めてみます。
財務省の緊縮財政路線 vs. その他の省庁
かつて中野氏を京大の准教授として招聘した京大教授の藤井氏は土木学者で、その立場は国土交通省をなんらかの程度で代弁するものとみてよいでしょう。他方の中野氏は経済産業省の官僚です。
つまり、ことは財務省 vs. 経産省・国交省ということになります。財務省の緊縮財政路線のなかで、公共事業が削減され、国交省が管理するインフラは劣化し、持続可能性が失われつつあります。他方の経産省も予算制約のなかで、思うような産業政策が打てないのでしょう。そうこうするうちに日本には「国際競争力」のある目ぼしい産業がなくなりつつあるようです。
ある意味で、経産省・国交省は財務省の緊縮財政路線の直接の被害者であるともいえます。
ただ、こう考えるとき、他の省庁についても事情は同じなのではないかとも思うのです。
農林水産省だって予算が足りないでしょう。農業の職業的魅力が小さいままで、就業者の高齢化が進んでいます。日本の食料自給率は一向に改善せず、食料品の海外からの輸入への依存が激しい状況です。
世界の人口増、気候変動、パンデミックや戦争等による世界的な物流混乱、シーレーン危機、世界の分極化過程で発動される経済制裁ないし兵糧攻めとしての輸出停止…そういった海外からの食糧供給を途絶させるリスクを考えるとき、この海外依存の大きさは大きな不安要因です。
石油の禁輸で半ばヤケになってしまった戦前の過ちを繰り返すようなことがあってはならないでしょう。
あるいは文部科学省はどうでしょうか。小中高に関して言えば、近年は学校教員の待遇があまりに悪く、募集しても定員が埋まらないというような話題をよく聞きます。
大学に関して言えば、独立行政法人化されて運営費交付金が機械的に削減されたり、あるいは予算のいわゆる「競争的」配分が強化されたりしていくなかで、日本の大学が研究機関として地盤沈下していることも周知の事実です。大学教員の雇用は不安定化し、腰を据えた研究ができなかったり、あるいは競争的な予算の獲得のための事務作業に忙殺されていたり、というわけです。
このように劣化を続けている教育と研究が、その実、国家の根本であることは論を俟たないはずです。
比較的にマシなのは厚生労働省でしょうか。ネット上でも国交省(インフラ)・農水省(食料)・文科省(教育・研究)の予算をもっと削れ!という意見はほとんど見ないが、厚労省の管轄である年金・医療関係の予算の削減を求める意見はしばしば見られます。逆に言えば、これまでそれほど予算が削られてきていないのでしょう。優秀な学生がみんな医学部を目指してしまうということも、厚労省の相対的優遇と関係していると言えるのかもしれません。
コロナ禍という擬似戦争的な緊急事態、政権与党を支えるシルバーデモクラシー、医師会の政治力、そして少子高齢化、そういった要因のために厚労省は緊縮財政下の予算削減を相対的に免れてきたのかもしれません。社会保障費の予算だけが年々膨張していることは事実でしょう。
財務省の緊縮財政路線と主流派経済学との共鳴
さて、ここ三十年を振り返るとき、このように財務省 vs. 他省庁という争いを見出すことができるわけなのですが、ここで財務省と共鳴関係にあったのが主流派経済学だとみることができるでしょう。
なぜ共鳴するかというと、競争的な市場で達成される均衡を重視する主流派経済学によれば、その均衡こそが最適な資源配分を実現するのであって、政府による規制や介入はそれを撹乱することにしかならないからです。
だから、主流派経済学は政府支出は少ないに越したことはないと考え、それが財務省の緊縮財政路線と合致したわけです。
より仔細に見てみましょう。以下は、この共鳴関係の平均的な意見の再現です。
国交省の公共事業に関しては、まずは土建屋との非競争的な癒着が心配です。土建屋は競争せずに政治家と結びついて仕事をもらっているのではないでしょうか。そして、競争にさらされることのない政府が作るものなど、そもそも碌でもないものに違いないのです。
経産省の産業政策に関しては、市場ならぬ国家の産業政策は成功するはずがありません。競争にさらされない政府や官僚にどの産業が伸びるかを見極める力などないのです。
農水省の農業政策に対しては「稼ぐ力」を強調しましょう。グローバルな市場競争で勝てないような農家は潰れてしまえばよく、日本国民は安くて競争力のある(が、いつまで安定供給されるかは不明な)海外産の食料を食べればいいのです。それぞれの国が比較優位がある産業に特化すること。それが世界にとって一番効率的なのです。
文科省の教育政策についても同様です。大学も「稼ぐ力」をつけるべきであり、研究者はもっと「競争」すべきなのす。それが良質の成果を生み出す。だから国家からの予算配分は減らし、競争的な予算を強化して擬似的な競争を作り出す必要があるのです。
経産省のイデオローグによる21世紀の『経産省宣言』
それにしても、『入門 シュンペーター』に直接関係のない話に深入りし過ぎたようです。
このような話を通じて私が言いたかったのは、本書『入門 シュンペーター』は、このような財務省と主流派経済学の共鳴状態が「諸省庁の争い」で他の省庁を抑圧してきたことに対して、ある仕方で経産省の(反新自由主義的な部分の)イデオローグであると思われる中野氏が放った反撃の一手であって、まさに21世紀の『経産省宣言』とでも言える内容になっているということです。
その本書の具体的な内容を、次節以降で追いかけてみることとしましょう。
本書の内容―21世紀のための『経産省宣言』
さて、本書の内容を見ていきましょう。先に私は、本書は一種の「経産省宣言」として位置付けられると言いました。
その意味は、この数十年間、財務省の緊縮財政論と主流派経済学が共鳴するなかで、他の各省庁は予算面で抑圧されるとともに、その果たすべき役割においても過小評価されるようになってきたのですが、本書は、そのようなイデオロギー的・現実的な状況に対して、産業政策を所管する立場にある経産省側からなされた反撃であるということです。
シュンペーターをこちら側に取り戻すということ
その反撃はいかにしてなされるのでしょうか。それはなんとなく「あちら側」、すなわち、財務省・主流派経済学側に属しているように思われているシュンペーターを「こちら側」に取り戻すことによってです。中野氏によれば、シュンペーターの真意はまさに財務省・主流派経済学の共鳴関係とは正反対の位置にあるのです。
シュンペーターは一般に「イノベーション」や「創造的破壊」という語で知られます。私たちはこれを「なんとなく」主流派経済学流の市場中心主義に親和的なものだと解釈しています。
主流派経済学によれば、市場では価格メカニズムによって需要と供給の一致としての均衡が達成されます。そして、独占的な供給者がいて価格が高止まりするのではなく、複数の供給者が互いに激しく競争をしていくなかで決定される価格での均衡においてこそ、供給者と需要者の全体にとってある仕方で最適な効用が実現されます。
このような仕方で主流派経済学は市場の意義を述べるわけですが、私たちはこれを「なんとなく」「イノベーション」や「創造的破壊」と結びつけて解釈しています。
すなわち、市場の競争のなかでこそ、イノベーションが生まれてくるということです。日本でイノベーションが生まれないのは、市場競争に対する国家の規制が厳しすぎるからであって、国家にぶら下がる利権屋が多すぎるからであって、国家の福祉にお世話になる怠け者が多すぎるからであって、大企業のような独占的な既得権益が新規参入者を潰して回っているからなのです…。こういった既得権益の岩盤を「創造的破壊」によってぶち壊し、市場競争を全面化すること。そのなかに「イノベーション」が生まれてくるはずだ、というわけです。
この主流派経済学の反国家主義が、財務省の緊縮財政路線と結びつきます。というのも、この反国家主義は政府予算の縮小を正当化してくれるからです。その考えによれば、国家の支出は、市場の競争にさらされない利権的な所得を生み出し、競争を阻害してイノベーションが生まれない環境を作り出すとされるからです。
さて、こういうわけですから、本書のシュンペーターを取り戻す試みは、この「イノベーション」と「市場の競争」との連想を断ち切り、既得権益めいており、鈍重で「イノベーション」を起こせそうにないとされている「大企業」をこそ「イノベーション」の場として再評価します。
そして、その「大企業」の機能が「株主資本主義」によって損なわれている現状を憂いた上で、残る希望を「国家」に見出すのです。そこでは国家による「産業政策」こそが「イノベーション」の源泉として見出されることになります。本書が実質的に「経産省宣言」といえる所以です。
この理路をもう少し詳しく追っていきましょう。
本書の内容の簡潔なまとめ
イノベーションの理論は「反」市場均衡の理論
中野氏が本書の冒頭近くで取り上げるのが、シュンペーターによる「静態的」な経済と「動態的」な経済の二分法、そして、「快楽主義的」な人と「精力的」な人の二分法です。
このうち「静態的」な経済と「快楽主義的」な人は、主流派経済学の語る市場均衡の経済に対応します。快楽主義的な人とは合理的に効用を最大化する経済人のことで、こういう人たちの集合的な行為の結果として、市場では均衡価格における需要と供給との一致が実現され、最適な資源配分が達成されます。
しかし、「精力的」な人は、このような過程に満足しません。そのような人は、創造の喜びや地位獲得の欲求に突き動かされて、何か新しいものを生み出そうとします。その人が「新結合」によって「イノベーション」を達成するとき、市場の均衡は破られ、経済は「動態的」になるというわけです。
ポイントは、主流派経済学風の市場競争とイノベーションを結びつける通俗的なイメージとは反対に、シュンペーターはイノベーションの理論を、主流派的な市場競争と市場均衡では捉えられない経済の現実を捉えるものとして構築していたということです。
「信用創造」が資本主義の定義を構成する
次の話題として、シュンペーターが主流派経済学で通説とされる商品貨幣論ではなく、昨今ではMMT派貨幣論などで広く知られるようになった信用貨幣論の立場をとっていたことが論じられます。
現代においては、銀行が貸出を通じた信用創造によって無から貨幣を創造しており、だから借金がなければ貨幣は基本的に存在しません。これを理解すれば、財務省流の緊縮財政論がいかに馬鹿げているかがすぐに分かるでしょう。
主流派経済学流の商品貨幣論では、貨幣はゴールドのようなモノ、有限な量のモノと考えられます。政府の国債発行は、この有限なモノを借り入れることで、借金だから返さなければならないと考えます。国の借金が1000兆円もあって大変だ、というわけです。
しかし、金本位制が終わった今、この商品貨幣論にはなんらの妥当性もありません。現代のシステムの描写として正しいのは信用貨幣論です。信用貨幣論の立場からすれば、借金がなければお金が存在しません。経済規模に応じてお金が増えるべきである以上、借金も増えていかなければなりません。民間が借金を十分にしないなら、政府が借金を増やさなければならないのです。だから、政府の借金の増大は単に必然でしかありません。さらにいえば、通貨発行権を持つ政府のいわゆる借金は実際には借金と考えるべきですらありません。
さて、この辺りはMMT派貨幣論を理解している人からすればお馴染みの議論であるわけですが、興味深いのは、中野氏によると、シュンペーターが信用創造の存在をイノベーションと固く結びつけ、そうすることで信用創造をまさに資本主義の要件そのものに数え入れているということです。
資本主義の本質はイノベーションにあり、イノベーションが実現するためには余剰資金が必要なのであって、それが迅速に確保できるためには貨幣が無から創造される信用創造の力が必要であるというわけです。
大企業の時代と「株主資本主義」によるその終焉
さて、初期のシュンペーターは、一般のイメージの通り「イノベーション」は現代でいうところのスタートアップ企業ないし起業家的な人々によって生み出されるという風に考えていたのですが、後期には大企業組織をイノベーションの担い手として重視するようになったといいます。
それには独占的な大企業が台頭し、にもかかわらず、さまざまなイノベーションによって人々の生活が豊かになっていったという20世紀前半の時代経験が反映されていました。
シュンペーターによれば、企業が繰り広げる競争は、完全競争ではなく独占的競争であり、そこでは企業は他の企業との差別化を通じて、自分だけの小さな独占市場を構築しようと試みています。競争は独占の反対語ではなく、企業は独占をするための競争をしているというのです。
このような独占市場が確保する競争の制限こそが企業に余裕をもたらし、企業を強くします。大規模かつ長期的な研究開発や設備投資が必要となる現代においては、イノベーションを生み出すには、この余裕が不可欠です。だからこそ、大企業がイノベーションの源泉として重要なのだというのです。
しかし、中野氏いわく、このイノベーションの源泉としての大企業の役割は、1980年代以降に「株主資本主義」の時代が到来することによって終焉を迎えます。その事態を理論化しているのがウィリアム・ラゾニックだといいます。
その議論を簡単にまとめてしまえば以下のようなことになります。すなわち、「株主資本主義」以前の企業は、独占的地位で得られた資金を長期的な研究開発や設備投資に充てていました。それがイノベーションの源泉となっていました。
経営者たちは、長期的な企業の発展を目標にして行動し、労働者たちを長期雇用することで、労働者の能力を高めていました。それもイノベーションの基盤となりました。
しかし、市場を重視する主流派経済学の影響で、株式市場こそが企業の価値を正しく評価できるとされるようになり、企業の目的は株主価値の最大化だとされるなかで、このような古き良き企業文化は変質していったというのです。
経営者たちは、自分たち自身が株式で報酬をもらうようになるなかで、短期的な株価上昇を至上目標とするようになりました。
株価、すなわち、株主にとっての価値を高めるには労働者に払う賃金はコストです。だから、労働者の賃金は引き下げられ、雇用は短期化されて、労働者の能力は下がりました。
さらに株価を上げるチート技のような自社株買いも解禁されて、企業の利益は、長期的な研究開発や設備投資ではなく、株主への利益配分である配当と、株価を上げるための自社株買いに使い込まれるようになりました。
このような「株主資本主義」への変質によって、大企業はイノベーションの担い手としての機能を失っていったというのです。
イノベーションの源泉としての国家
中野氏の見立てでは、かつて日本的経営と呼ばれたものは、シュンペーターが論じたような、イノベーションを可能にする理想的な大企業の経営だったのですが、日本は「株主資本主義」に転換することで、その良さを失ってしまいました。
しかるに、他方、「株主資本主義」の本場であるアメリカではGAFAのようなイノベーションが起きています。これはどうしてでしょうか。
ここで言えることは二つある。一つはそれらの企業が、はじめは違うにしても、基本的には典型的に独占的な地位を確立した大企業であり、圧倒的な余裕を持っているということです。これはシュンペーターの議論に反しません。
そして、もう一つが、こちらがより重要なのだが、アメリカにおいて国家が果たした役割です。
この国家の役割を追求したのが、中野氏によれば、マリアナ・マッツカートです。
そもそも、長期的な視点での研究開発や設備投資がイノベーションを生み出すのだとすれば、その余力をもっとも持っているのは、(政府の借金を問題視する誤解を取り除けば)大企業ではなく国家です。だから、国家の評価は大企業の評価の延長線上にあります。
そして、実際、半導体にしても、コンピューターにしても、インターネットにしても、もっとも決定的で基盤的なイノベーションといえるものは、アメリカ政府が中心となって推進した宇宙開発や軍事研究の副産物の側面が濃厚なのです。シリコン・バレーはもともと軍需用の半導体の製造会社の集積地だったそうです。
中野氏によれば、マッツカートはのちにMMTを受け入れることになります。MMTはシュンペーターの貨幣論を継承するものであり、マッツカートはシュンペーターのイノベーション論と企業論を継承しています。シュンペーターから発したこの二つが合流するのは当然ということになるのでしょう。
こうして議論は、財務省的な緊縮財政論を信用貨幣論的な前提でもって無効化したうえで、主流派経済学の市場競争論では捉えられないイノベーションの担い手として国家を認識することへ向かっていきます。
それは、すなわち、国家の産業政策の意義の再評価に他なりません。本書が実質的に『経産省宣言』だといえる所以です。
いくつかの感想ないし論点
いくつか、感想というか論点というか、今後考えたいことを述べておきたいと思います。
一つは、「競争」の評価をめぐる問題です。本書が説得的に述べているように、イノベーションは主流派経済学のいう市場競争とは少し異なっており、同じモノをめぐって同じ市場で価格競争をするのではなく、むしろ差異化によって小さな独占市場を作り出そうという競争です。そして独占が生み出す余裕こそが、長期的な研究開発や設備投資によるイノベーションを引き起こすということも確かでしょう。
ただ、だからといって、主流派経済学流の競争も意義がないわけではないようにも思います。主流派経済学流の競争が働き、そこでは利潤が得られなくなっていくからこそ、イノベーションによる独占的競争が駆動されるという側面は否定できないように思われのです。その意味では、主流派経済学流の競争を防いでしまう国家による規制や介入などはない方が望ましいという可能性はあるでしょう。
要するに、真実は中庸にあるように思うのです。過度の市場競争は企業に余裕を失わせ、積極的なイノベーションを起こす体力を失わせます。他方で、市場競争の不在は現状に甘んじる誘因となり、こちらはイノベーションを起こそうという気概を失わせます。
問題は、この点をどのように考えるかです。適切で適度な競争環境はいかなるもので、それはいかにして制度的に担保されうるのでしょうか。
もう一つは、保守と経済思想の関係という問題です。中野氏の立場は、この語を私は悪い意味で使うつもりはないのですが、ある程度まで「国家社会主義」的に見えます。
中野氏自身も、経済に占める国家の役割が大きくなっていくという意味での社会主義化の長期的な傾向をシュンペーターの議論から引き出す中で、「社会主義=左翼」という批判を意識しているようです。その流れで「社会主義=左翼」の反対側にある「新自由主義=保守」とする認識を批判し返しています。
社会主義は左翼で、その反対に新自由主義が保守だという認識には、私自身も違和感を持ちます。それこそ左翼のマルクスが言ったことではないかと言われればその通りですが、無制限の資本主義ないし市場経済とは既存の一切の秩序を流動化させていく力であり、どう考えても保守的ではありません。
ハイエク流に市場経済は自生的秩序だから保守だなどといわれても、私にはピンとこないのです。この言説には「歴史的に市場経済は本当に自生的か」「規制改革で市場競争を生み出すというのはもはや自生的でない」等、いろいろと問題があると思いますが、ここでとりあえず指摘したい論点は、自生的秩序だから保守だというの言説の背後にある、保守をとにかく反設計主義とする前提が正しいかどうかです。
既存の秩序を破壊するものは設計主義だけではないように思うのです。秩序破壊的な運動が自生的に生じることもあるのであって、資本主義とはその一例であるように思われるのです。とすれば、一定の設計性は伴うにしても、自生的秩序ならぬ、自生的秩序破壊である資本主義を適切に制約する制度を設計することこそが秩序を保守することにもつながるように思うのです。
このように考えていくとき、なぜ保守と新自由主義が結び付けられて考えられるようになったのか、そしてそれはどこまで妥当なのか、もう少し自分なりに考えてみたいと思うのです。


※コメントは最大500文字、5回まで送信できます