この記事では本サイトでの信用貨幣論の関連記事の概要を紹介し、信用貨幣論についての私の考えの全体像を簡潔に提示します。
信用貨幣論について一番最初に取り扱ったのが以下の記事で、信用貨幣論の基本の記事になります。教科書的に普通よく言われていることをまとめています。基本的な論調はMMT派的なスタンスで、主流派経済学の商品貨幣論よりも、MMTも採用している信用貨幣論の方が正しいよね、というものです。
ただ、最後の余談でこの二項対立を崩して、信用貨幣論って言っても、信用貨幣の基本はモノを引き渡す債務なんだから結局は商品貨幣論なのではという議論を提起して、私の最終的な立場である「信用貨幣の弁証法」の立場への導入としています。

時間的にはこれより前ですが、信用貨幣論と密接に関わる信用創造についての基本の記事が以下です。こちらは信用創造について又貸し説と万年筆マネー説を紹介し、MMT派的なスタンスで万年筆マネー説の方が正しいとしています。
ただ、二項対立を崩すスタンスで、又貸し説でも銀行からの借金でお金が増える点はどちらも変わらないと、両説の違いを相対化しています。また、信用創造の制約条件についても詳細に論じています。

三番目の記事は、私にとって曖昧だった信用貨幣論と信用創造の関係性を明確にするための記事です。ここで、この両者の関係を明確にするために「信用貨幣の弁証法」の枠組みが必要となりました。
当サイトで「信用貨幣は商品貨幣から自立を達成していく運動だ」と捉える「信用貨幣の弁証法」が登場した最初の記事となります。信用貨幣の自立の結果、信用創造が可能になり、また信用創造そのものが信用貨幣を自立させるものでもある。信用創造は信用貨幣が自らの依存性を克服し自立していく「信用貨幣の弁証法」の重要な一場面なのです。

四番目の記事は「信用貨幣の弁証法」を全面展開した記事で、信用貨幣論とは何か、それと商品貨幣論の関係、それと信用創造との関係、それとMMTの国定信用貨幣論の関係の全てを「信用貨幣の弁証法」という一貫した理論的枠組みで語った記事です。
それは「信用貨幣の弁証法」という「信用貨幣が何段階にもわたって自らの依存性を克服し自立性を高め、より高次な形態へと展開していく物語」のさしあたりの終着点に、MMTの国定信用貨幣論と租税貨幣論を位置付けることで、MMTの哲学的な正当化、すなわち、今回の意味では歴史的-論理的な正当化を実行することになりました。
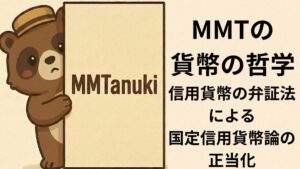
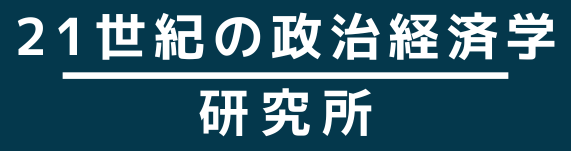
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます