この記事は約10分で読めます。
この記事では、話題の新しい経済理論で、今後の日本経済を考える上で必須の視点であるMMT(現代貨幣理論)について、初学者にもわかりやすい入門的な解説を行います。
この記事を読むと「税は財源ではない」「国債は借金ではない」「政府の赤字はみんなの黒字」などの、MMT派や、それに影響を受けた人々の主張の背景がよく理解できるようになるはずです。
 MMTanuki
MMTanukiぼくはMMTanuki、一緒にMMTを学ぼう!今回は初級編!



会計的な思考を活用してMMTの語るお金の仕組みを完全解説した中級編を求める方はこちらの記事をご覧ください。
さて、MMTはしばしば、お金や財政についての現実を説明する「説明的な部分」と、政府が取るべき政策指針を述べる「処方箋的な部分」に分けられます。
今回は、MMTの「説明的な部分」を紹介し、それが正しいのかを検証します。
MMT(現代貨幣理論)の簡単な入門―それは「いまのお金の説明」です
さて、MMTは、Modern Monetary Theoryの略で、これを日本語に訳すと「現代貨幣理論」となります。日常的な言葉でいえば、「いまのお金の説明」ということです。
ここで「いま」というのは、正確には1971年以降のことです。この年にアメリカのニクソン大統領が、ドルと金(ゴールド)の交換を止めることを宣言しました。こうして政府が発行するお金とゴールドが交換できる仕組み(金本位制)が終わりました。
この金本位制が終わった後のお金の仕組みを説明するのが、MMTです。これまでの経済学は、このお金の変化に対応できていないため、MMTという新しい理論が必要とされたわけです。
なぜ「税は財源ではない」のか?―「主権(=国定)貨幣論」
さて、このように金本位制が終わったいまとなっては、お金は政府が、なんらのモノによる裏付けもなく、決定し発行するものになっていますし、そうでしかありえません。円やドルは、ゴールドの代わりとしてではなく、政府がこれがお金だと決定し、発行したから存在しているわけです。
すると、「税は財源ではない」ということが分かるでしょう。政府が円をお金の単位として決定し、その円をまず発行しなければ、円はまだ存在しませんから、税金として円を集めることはもできません。政府が円を発行するまえに「財源」として税を徴収しようとしたって、そんなことは不可能なのです。
税が政府の財源なのではなく、政府による円の発行と支出が、税自身の「財源」なのです。税の徴収ではなく、政府によるお金の発行と支出が先、これがMMTのいうスペンディング・ファースト(=「政府支出が最初」)という原則です。これに基づいてMMTは「税は財源ではない」と主張します。政府の根源的な財源はつねにお金の発行です。
この、お金は政府が発行するものだという認識を、少し難しい言葉で「主権貨幣論」「国定貨幣論」などと呼ぶことができます。それは政府の通貨発行権に焦点を当てるのです。
「税は財源ではない」のに、なぜ税は必要か?―「租税貨幣論」
では、税は要らないかといえば、そうではありません。MMTにとって、税は財源ではありませんが、税がなければ政府のお金はそもそも機能しません。
MMTは、政府が「円で徴税するぞ!」と宣言し、それを実行するからこそ、ゴールドのようなモノの裏付けが一切ない政府発行の円を人々が受け取るようになり、それがお金がお金として機能する起点となるのだと考えます。税は財源ではありませんが、「税がお金を動かす(Tax drives money)」というわけです。
この税がお金の流通の基礎となるという議論を、少し難しい言葉で「租税貨幣論」といいます。
「国債は借金ではない」のに「国債」がある背景―「信用貨幣論」
以上から、「国債は借金ではない」ということも理解できるでしょう。政府はお金をなんらのモノの裏付けなしに発行しています。そんな政府がお金を使うために、それを誰かから借りなければいけないなんて、本質的にはあり得ないという話です。
だから、政府がお金を使うのに国債を発行し、なにか借金をするかのように言っているのは見かけ上の話にすぎません。では、なぜそんな見かけをとっているのでしょうか。ここには、上述の「主権貨幣論」や「租税貨幣論」とはまた別のお金についてのストーリーが関わっています。
それは誰かが銀行から借金をするときに、その借金を裏面としてお金が生まれる「信用創造」と呼ばれる仕組みです。私たちが100万円を銀行から借りるとき、銀行は私たちに100万円の預金を発行します。このとき100万円のお金(預金)がどこからともなく生まれてきます。これが「信用創造」で、それは、いわばお金が借金を裏面としてのみ生じるという仕組みです。
中央銀行が絡んでくるため、政府については話が少し複雑なのですが、本質は変わりません。初歩的な認識としては、政府もこの「信用創造」の仕組みに従っており、お金を発行し支出するときに「借金」をするという体裁をとっていると理解すれば、大きく間違ってはいません。
国債が借金であるというのは見かけ上のことです。この理解に基づき、MMT派は、「(何か恐ろしいものとして宣伝されている)政府債務(=国の借金)残高は、実は政府によるお金の発行残高に過ぎない」と主張します。
このもう一つのお金についてのストーリーは、一般に「信用貨幣論」と呼ばれます。ここで「信用」とは貸し借りの関係、平たく言えば「借金」のことで、お金を借金と強く結びつけて捉える考え方です。ここにも、いろいろと複雑な論点があり、以上の記述は大雑把なものですが、初歩的な理解としては以上で十分です。
↓「信用創造」の詳細と、それを日銀が認めていること、また「信用貨幣論」についての詳細は、以下の記事をそれぞれご覧ください。




なぜ「政府の赤字はみんなの黒字」なのか?―「部門間収支」
MMTの「説明的な部分」の紹介の最後に、「政府の赤字はみんなの黒字」という言葉も解説しておきましょう。MMTは、難しい言葉でいうと「部門間収支」にあらためて光を当てました。それは経済を「政府・民間(企業や家計)・海外」の大きく三つに分けて考えてみるという方法です。
ここで海外を取り除いて考え、政府と民間だけを見ると、誰かの赤字は誰かの黒字ですから、当然、「政府の赤字は民間(=みんな)の黒字」となるわけです。誰かの赤字は、誰かの黒字ということは以下の例を考えれば分かるでしょう。
最初にAさんもBさんも100万円を持っており、一年間、二人でいろいろな取引を行います。一年の終わりに、Aさんが120万円を持っており、20万円の黒字だったとしたら、この世界のお金は200万円しかありませんから、Bさんはかならず80万円しか持っておらず、20万円の赤字です。こういう意味で誰かの赤字は誰かの黒字なのです。
「政府の財政赤字が大変だ!」と言われますが、その裏側で(海外を考えなければ)必ず「みんなの黒字」が増えています。逆にいえば、政府が財政黒字になるとき、みんなは赤字に転落します。「政府の財政赤字が大変だ!」と騒ぐのに、政府が財政黒字になったときに「みんなの赤字が大変だ!」と騒がないのは奇妙ではないでしょうか。
なので、普通の人の視点から見れば、「財政赤字=みんなの黒字」の方が「財政黒字=みんなの赤字」よりもよいことは明らかでしょう。そして、これは客観的にも言えます。政府はいくら赤字を抱えても、国債が本質的に借金でないために何も困りませんが、民間が大きな赤字を抱えると、実際に借金の返済で首が回らなくなり、経済が不安定化するのです。
MMT(現代貨幣理論)は正しいのか?—事実と論理の観点から
まず結論を述べると、これまでに述べたことに関して言えば、MMTは正しいと考えられます。
ある言葉が正しいというとき、私たちは主に二つの意味でこれを使っています。一つは、それが事実と一致しているという事実的な正しさです。もう一つは、前提が正しければ、その前提から論理的に帰結する結論は正しいという、論理的な正しさです。
この観点から、上の議論を整理してみましょう。
「主権貨幣論」の検証―事実的かつ論理的に正しい
まず、お金がゴールドに裏付けられていた金本位制が終わり、いまやお金は政府がなんらのモノの裏付けもなく発行しているという「主権貨幣論」は事実的に正しいでしょう。そして、これを前提として認めるなら、そこから「税は財源ではない」ことや「国債は借金ではない」ことは、論理的に出てきます。
お金は政府が発行するものだとすれば、税を財源にすることは論理的に不可能です。だって、まず政府がお金を発行していなければ、そのお金を税として集めることもできませんから。税が政府支出の財源なのではなく、政府支出が税の財源なのです。
そして、政府がお金を発行できるなら、その政府がそのお金を誰かから借りなければいけないということもあり得ないことは明白でしょう。
こういうわけですから、「税は財源ではない」ことや「国債は借金ではない」ことは、「主権貨幣論」の事実的な正しさに基づいて、論理的に正しいと言えるでしょう。
「租税貨幣論」の検証―ひとつの有力な仮説として
つづいて、上のように「モノの裏付けなく発行されるお金が流通するのは、政府がそのお金での納税を強制するからだ」という「租税貨幣論」はどうでしょうか。
これは「主権貨幣論」とは違って、事実の説明ではなく、お金が流通しているという事実に対して、その理由を説明するものなので、単純な「事実的な正しさ」の対象とはなりません。それはむしろ、さまざまな事例を通じて、その妥当性が検証されるべき仮説であるに止まります。
また、「租税貨幣論」の問題点として、それが結局は「暴力貨幣論」に還元されるということがあります。なぜ、税金を課すことで人々にお金を受け取らせることができるのでしょうか。それは税金を払わなければ、究極的には捕まるからだ、ということになります。要するに、「租税貨幣論」といっても、最終的な根拠は国家による暴力にあって、租税が真の本質ではないようなのです。
ただ、逆にここまで考えると、「租税貨幣論」はお金がだいたい国家単位で流通しているという現実と極めて整合的だとも言えそうです。お金がほとんど国家単位で流通しているという事実は、お金の流通に国家だけが持つ「暴力」という要素が決定的な役割を果たしているという仮説を説得的なものとしてくれるわけです。
本当のところ、日銀当座預金で何ができるかを考えることで、租税貨幣論を事実的な正しさというレベルで根拠づけることもできるのですが、少しむずかしい話になりますので、今回は省くことにします。
「信用貨幣論」と「部門間収支」の検証―どちらも事実的に正しい
現代において、お金の大部分は銀行預金であり、それは借金によって、その裏面として生まれるという意味での「信用貨幣論」はどうでしょうか。これは端的に事実で、事実的に正しいといえます。それは以下の国会の動画で日銀が認めている通りです。
また「部門間収支」と関連する、誰かの赤字は誰かの黒字、ある部門の赤字は他の部門の黒字、したがって、「政府の赤字は民間(=みんな)の黒字」といった主張も、どれも事実的に正しいといえるでしょう。
以上のような形で、これまで述べてきたことに関していえば、MMTは概ね正しいと評価することができるでしょう。
まとめ―MMTの「説明的な部分」を認めることから出発しよう
MMTの説明的な部分は、現代のお金は何らのモノの裏付けなしに政府によって発行されているという「主権貨幣論」、税の役割は徴税の義務を課すことで政府発行のお金が受け取られるようにすることにあるという「租税貨幣論」、お金と借金は深く結びついており、現代のお金は銀行で借金をすると発行される銀行預金だという「信用貨幣論」の三つの柱からなっています。
このうち「主権貨幣論」と「信用貨幣論」は文句なしに事実的に正しく、「租税貨幣論」もお金が流通する根拠として有力な仮説だと評価でき、結果として、MMTの「説明的な部分」はおおむね正しいものと評価できます。今後の経済や社会や政治についての考えは、この認識を出発点とするべきなのです。
MMTanukiと暗渠づたいおじさんの余談



もちろん、今回学んだことは初歩の初歩の初級編!
MMTには「処方箋的な部分」もあるし、そちらに関しては、マクロ経済分析も関わってくるから、正しいのかどうか、論争点も多いんだ。



あと、MMTの「説明的な部分」にしても、流石にこれだけじゃ十分じゃない。やっぱり複式簿記的な思考を使って、現代のお金の生まれ方と動き方と消え方を、会計的にしっかり理解できた方がいい。
それを通じて、銀行と中央銀行と政府の関係みたいな、MMTのいわゆる「債務ヒエラルキー」もしっかり理解したいね。これらは中級の課題だといえるかもしれない。
↓MMTの「説明的な部分」についての中級編の記事ができました!
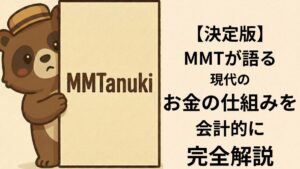
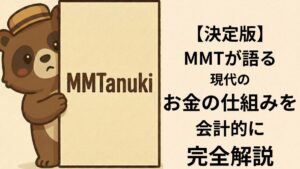
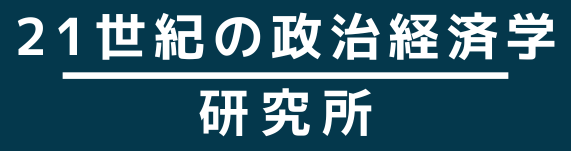

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます