この記事は約9分で読めます。
近年、MMT(現代貨幣理論)派やそれに影響を受けた人々が「税は財源ではない」と主張することが多くなっています。
この記事では、この主張の背景と射程をわかりやすく説明します。
具体的には、①「税は財源ではない」という根拠、②それでも税に認められる役割、さらに③税が財源ではないとされる場合の「真の財源」と「財政規律」の考え方の3点を解説します。
この記事を読むことで、「税は財源ではない」「税がお金を動かす」「財政規律はインフレ率」「財源は供給能力」などのMMT的な主張をしっかり理解できるようになるはずです。
 MMTauki
MMTaukiぼくはMMTanuki。この記事を読めば、MMT派がよく使うこれらのキャッチフレーズをしっかり理解できるはず!
「税は財源ではない」理由―現代のお金は政府が作ったものにすぎない
「円」というものについて考えてみてください。それはコメやゴールドのように自然に存在するものではありません。それは田んぼに生えてもいないし、金山に埋まってもいない。ましてや、海を泳いでいたり、山で採れたりもしません。円は自然物ではありません。
円は、政府が円をお金の単位として決定し、円を発行することによってのみ存在します。
この事実を認めると、「税は財源ではない」ことは明らかでしょう。政府が出来たとき、まず最初に税金として円を集めて、その円を支出しようなどと考えても、円はまだ存在していません。政府が円を発行しなければ、それを税として集めることもできません。だから、税は財源ではなく、逆に「政府によるお金の発行が税の財源」なのです。
もちろん、コメやゴールドを税として集めていた時代には、このことは当てはまりません。ただ、1971年にアメリカがドルとゴールドとの交換をやめて以降、お金とゴールドその他の自然物との関係は断ち切られました。だから「現代」においては、「税は財源ではない」が当てはまります。だからこそ、MMTは「現代」貨幣理論なのです。
この、現代のお金は、政府が何らの自然物の裏付けなしに発行した、政府による作り物だという認識により、MMTの立場は「主権貨幣論」「国定貨幣論」などと呼ばれます。
「税がお金を動かす」―税にはお金をお金にする機能がある
さて、「税は財源ではない」からといって、MMTは税は不要だと考えているわけではありません。MMTは税にいくつもの機能を担わせています。その第一は、そもそも税が政府の発行するお金をお金として機能させるというものです。
つまり、政府が「円で納税しなさい!」といって、その納税を強制するからこそ、人々は政府が何らの裏付けもなく発行した円を集める必要が生じ、円を受け取るようになるというのです。そして、人々が円を受け取るからこそ、その人々からモノやサービスを買いたい人も、円を後で支払うために受けとるようになる。こうして税が起点となってお金がお金として機能しだすのです。
これが「税がお金を動かす」というMMTの議論で、この税がお金の流通の起点となるという認識は「租税貨幣論」と呼ばれます。
また、MMTは税はさまざまな機能を担いうると考えます。たとえば、再分配による格差の縮小の機能(累進所得税)、タバコや環境汚染などの望ましくない行為に罰金を課して抑制する機能(タバコ税など)、景気の過熱を抑え、景気の減速時にはそれを刺激する自動安定化装置(累進的な所得税や法人税)などです。
税はさまざまな機能を持ち、その最大のものはお金をお金として流通させる機能ですが、それでも「税は財源ではない」のです。
「財源は供給能力」―税が財源ではない世界の「財政規律」
さて、「税は財源ではない」とすると、「財政規律」はどうなってしまうのでしょうか。
普通、私たちは自分たちの生活について、「給料以上にお金を使っちゃダメだよね」と思っており、給料以上にお金を使って、そのために借金が増え過ぎたらマズいと考えています。
この生活実感というか、家計簿感覚をそのまま国家に移しかえたものが、いまの政府が掲げている「プライマリーバランス黒字化」という「財政規律」です。これは大雑把にいえば、政府の支出を政府の収入である税収以下に抑えようというものです。
しかし、「税は財源ではない」、そして「財源は通貨発行」ということになれば、「支出を収入以下に」という財政規律は意味を失います。どうなるのでしょうか。MMTはしばしば「国債は無限に発行できる」と主張する「トンデモ理論」と批判的に紹介されますが、この批判の通りなのでしょうか。
いえ、そうではありません。確かにMMTは、お金を政府が発行するものとみなし、だから政府はお金を借りる必要はなく、国債は借金のような見かけをしているが、その実態はお金の発行だと考えます。そして、お金を借りるとなれば、それは貸し手によって制限されますが、発行するなら、そこには限度はありません。政府はお金を無限に発行「できる」。
しかし、MMT派やそれに影響を受けた人々は、政府はお金を無限に発行「できる」と言ったからといって、それを「するべき」と言っているわけではありません。
政府がお金を発行して自ら国内の財やサービスを買い漁ったり、国民にお金を渡して、国民が財やサービスを買い漁るとすると、それらの需要はどこかの時点で国内で供給できる財やサービスの総量を上回ってしまいます。
すると、限られた財やサービスに大量のお金が殺到することになり、物価の上昇、つまり、インフレが引き起こされることになります。こうなったら、それ以上のお金の発行には意味がありませんし、経済に無用の混乱を引き起こすだけです。
だから、政府がお金の発行をすべきなのは、需要が供給に対して少ないとき、財やサービスを供給する能力、さまざまな資源や設備や労働力が国内に余っているときです。そのときには政府がお金を発行して、国民の側の余剰能力を活用することで、国民に働き口と所得を与えると同時に、国民に財やサービスを供給することができます。
たとえば、不本意に失業してしまっている人を政府が雇って街の掃除をしてもらえば、その人は働き口と所得を得ますし、他の人々は綺麗になった街で気持ちよく過ごすことができるというわけです。
このように考えてくれば、「財源は(本質的には)供給能力」「財政規律はインフレ率」という主張も理解できるでしょう。
供給能力(資源・設備・労働力)が余っているならば、政府はお金を発行して、それを活用することで社会をより良くできるのです。不本意に失業している人に仕事と所得を与え、他の人々に財やサービスを供給できるわけです。この意味で「財源は供給能力」なのです。
その財源の限界はどうわかるでしょうか。可能な供給の上限を需要が上回ってきていること、つまり供給能力がフル活用(完全雇用)されつつあることを示すインフレ率の上昇によってです。だから、政府はたとえば「2~4%」などの許容できるインフレ率の範囲を設定して、インフレ率がそれを大きく下回ったり上回ったりしないように財政政策をコントロールすればよいのです。
以上のことから、MMT派や、それに影響を受けた人々は、政府にとって重要なのは「即座に無限に発行できる」お金などではなく、実際に財やサービスを生み出す供給能力であり、具体的には資源や設備やインフラや労働力や知識や技術だと考えます。これらは限られており、時間と労力を費やさないと生み出すことも維持することもできません。
日本ではいまだに「首都直下型地震や南海トラフ地震が起きたときの復興のために財政余力を確保しておかなければならない」「そのためにいま政府はお金を節約をしておかなければならない」などという論調がみられます。これは完全に狂った議論です。
お金など政府は即座に無限に生み出せます。他方で、いまお金を節約することで、老朽化したインフラを脆弱なまま放置するのみならず、それによって建設関係の供給能力も維持できなくしてしまうならば、地震による被害はそれによって大きくなるのみならず、その復興にも多大な時間がかかるという事態になるのです。これほど非合理的なことがあるでしょうか。
この記事の内容のまとめ
この記事では、お金は政府が何らの自然物の裏付けなく発行するものだという「主権貨幣論」的な事実から出発し、お金の発行が納税に先行しなければならない以上、「税は財源ではない」こと、にもかかわらず、モノの裏付けのないお金が人々に受け取ってもらえるために税という仕組みが必要であること、つまり、「税がお金を動かす」という「租税貨幣論」を説明しました。
その後、「税は財源ではない」として、では財源は何かというときに、もちろん、それは表面的には国債発行という仕方等で行われるお金の発行なのですが、より本質的には、政府が発行するお金で買う財やサービスの供給能力が余っていることだと論じました。それが余っていなければ、インフレが生じて経済的な混乱が生じるだけだからです。だから、「財源は本質的には供給能力」であり、「財政規律はインフレ率」なのです。
そして、最後に、政府が重視すべきはいくらでも生み出せるお金を節約することではなく、資源や設備やインフラや労働力や知識や技術など、財やサービスを実際に生み出すために必要な供給能力であるということを強調しました。
政府にとって重要なのは、現在の国民がその能力を望む限り活用できるよう状況を作り出し、その働きが、現在の国民による、より大きな果実を享受につながるとともに、将来の国民が享受できるものの量を決定する、未来の供給能力の増大や効率化にもつながるようにすることなのです。
MMT全般の理解を深めたい方は以下の記事をご覧ください。上が入門編、下が中級編です。
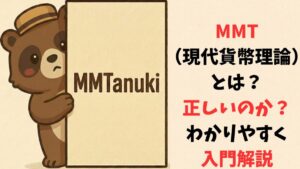
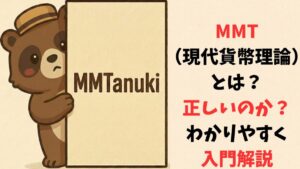
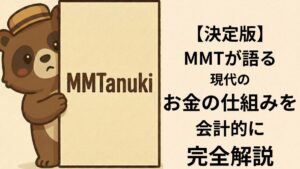
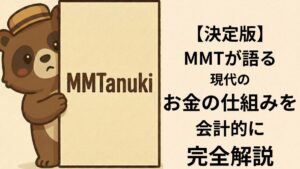
MMTanukiと暗渠づたいおじさんの余談—MMTの政策論について



「インフレ率を見ながら財政政策をコントロールする」みたいな表現は、本家MMTには怒られちゃうかも。本家MMTは、こういう政府が状況をみてやったりやらなかったりする「機動的・裁量的な財政政策」ってあんまり好きじゃないんだよね。



本家MMTは「インフレを引き起こさずに完全雇用を実現する」という目標を立てていて、その最良の方法は、働きたい人全員を政府が最低賃金で雇用していくJGP(就業保証プログラム)だと言っているからね。政府がいろいろな状況を見ながら機動的にやったりやらなかったりする財政政策だと、どこかでボトルネックが生じて、完全雇用を実現するまえにインフレが起きてしまうと考えているらしいね。



そうそう。あと、裁量的な支出は、利権政治みたいな感じで、恩恵が一部のすでに豊かな人々に偏ったり、あるいは局所的なバブルを発生させたりといったことにも本家のMMTは警戒的だよ。だから「インフレ率を見ながら政府が裁量的・機動的に財政政策をコントロールする」というのは、本家MMTというより、MMTに影響された人たちの主張と言った方がいいかも。でも、日本でもこういう人の方が、JGPを主張する本家MMT的な人よりも多いんだよね。



ただし、本家MMTの人たちも、グリーン・ニューディールとかには好意的だと思うから、裁量的な財政政策を完全否定して、JGP一本というわけではないよね。とりあえず言えるのは、MMTは現代のお金の現実を説明する「説明的・記述的」な部分にはかなりのコンセンサスがあるけれど、その上に乗っける「処方箋的」な部分、つまり、政策目標と政策手段に関しては、いろいろな立場があるということくらいかな。
MMT全般の理解を深めたい方は以下の記事をご覧ください。上が入門編、下が中級編です。
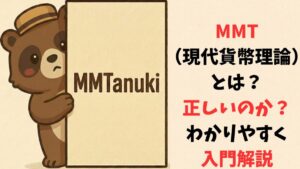
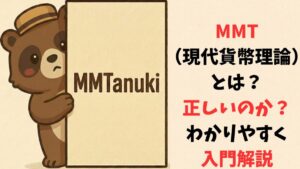
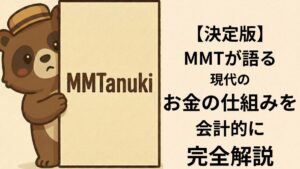
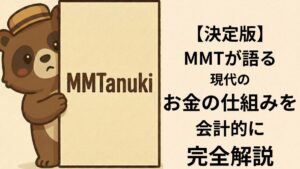
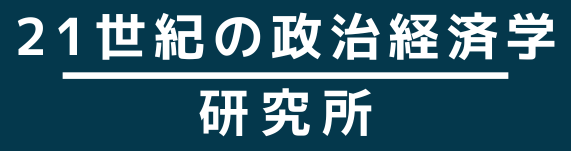

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます