この記事は約17分で読めます。
時間のない方はこちらの3分最速まとめ版の記事をご覧ください。
この記事ではリチャード・クーの『「追われる国」の経済学 ポスト・グローバリズムの処方箋』を解説的に要約します。
本書の英語タイトルをそのまま訳すと、『マクロ経済学のもう半分とグローバリゼーションの運命』となっています。このタイトルの通り、本書のテーマは「マクロ経済学のもう半分」で、これまでのマクロ経済学であまりテーマとされてこなかった「投資不足」の状況を扱うものです。
この「投資不足」を論じるにあたり、著者のクー氏は二つの原因を持ち出してきます。そのうちの一つ、中長期的で慢性的なものがグローバリゼーションにおける「追われる国」という立場であり、もう一つ、これと比較すれば短中期的で急性的な「バランスシート不況」という状況です。以上が本書のもっとも短い要約になるでしょう。
この記事では、第一節で、なぜクー氏が投資不足を扱うのか、その前提を確認した上で、第二節で「追われる国」の問題、第三節で「バランスシート不況」の問題をそれぞれ扱います。
その後は、著者の政策提案として、第四節では金融政策から財政政策への重点シフト、第五節では構造改革について、それぞれまとめます。最後の第六節では、本書の印象的な一節を紹介して、そこから少し議論を敷衍することでまとめに代えたいと思います。
 積極グマ
積極グマ積極財政を肯定するためには需要不足を指摘しなきゃいけないんだけど、クー氏は「需要」を構成する「消費」と「投資」のうち、「投資不足」の方に焦点を合わせているんだね。



そうそう。「需要不足の経済学」を完成させるには「消費不足」も考えるべきで、そちらは大阪大学の先生である小野善康の小野理論が参考になるよ。僕はクー氏と小野氏の理論を合わせることで現代のマクロの状況をもっとも的確に概観できると思っている。
なぜ投資不足に注目するのか?—貯蓄に見合う投資が必要な理由
まず著者が本書の冒頭近くで語っている例え話を簡単に再現しましょう。
AとBの二人だけの経済があるとします。はじめAだけが1000円の現金を持っており、Bが1000円の米を売っています。AがBから米を買うと、1000円の現金はBに移ります。ここでAも実は1000円の水を売っているとします。Bが水を買うと1000円は再びAに移ります。これはいつまでも続けることができ、1000円がAとBの間を行ったり来たりしながら、AとBは米と水をそれぞれ手にして生活を続けることができます。
これはAもBも所得を全て消費に回すパターンです。
ここでBが初めに1000円を得たとき、将来に備えて貯蓄をしようと思って、100円を貯蓄に回すとします。すると、BのAへの支払いは900円になります。とすると、次のAからBへの支払いも最大900円になるでしょう。あるいは、所得が減ったAも将来に備えて10%の貯蓄をしようと思えば、それは810円にまで下がるかもしれません。そして、所得が減ったBは…。
これはAもBも所得を全て消費に回すのではなく、一部を貯蓄するパターンです。
ここで、誰かの支出は他の誰かの所得ですから、上の例で分かる通り、自分の支出減は、他者の所得減とその結果としての支出減を通じて、自分の所得減に跳ね返ってきます。こうして生じる消費と所得の縮小スパイラルは、これ以上は生きるために消費を切り詰められないというレベル、最低限の生活レベルで初めて止まることになります。
これは個人個人の賢明な判断(将来に備えて貯蓄をしよう、収入が減って不安だから貯蓄をしておこう)が、社会全体では悲惨な結果につながるという、典型的な「合成の誤謬」であり、「貯蓄・節約のパラドックス」です。
これが起きないようにするためには、この貯蓄を補うだけの別の支出がなければいけません。それがこの貯蓄を借りて企業が行う「投資」に他なりません(もちろん、MMT派な私は投資が貯蓄から行われるとは考えず、このようには表現しませんが)。だから、問題はこの投資が貯蓄と同じだけ行われるかどうかなのです。
先に進む前に、ここで私から一点コメントをしておきます。著者はなぜ「消費」には注目しないのかという点です。
「失われた30年」を理解するための「需要不足の経済学」の、クー理論と並ぶもう一つの柱となる「消費不足の経済学」と呼べる小野理論によれば、ケインズは所得のうち消費に回る割合をあらかじめ決まった「消費関数」という形で前提してしまった結果、投資の増減しか問題にできないという視野狭窄に陥りました。
私には、本書もこの点ではケインズを継承しているように思われます。著者は消費に注目しない理由を表立って述べているようには思われないからです。これが、「投資不足の経済学」である本書の議論は「消費不足の経済学」としての小野理論によって補完されるべきだと私が考える理由です。
さて、話を本筋に戻しましょう。
このように、著者によれば、所得から消費を差し引いた後に残る貯蓄と同じだけの投資が存在することが、経済が縮小しない条件です。だから、繰り返しになるが、問題は投資が貯蓄と同じだけ行われるかどうかなのです。
伝統的な経済学では、投資が貯蓄と同じだけ存在することを保証するのが、お金の価格としての「金利」です。
それは以下のように考えます。投資は資金需要、貯蓄は資金供給です。どんなものでも需要より供給が大きければ価格が下がり、それに応じて需要が増えるとともに供給が減って、いずれは需要と供給が一致します。これが価格を通じて需要と供給を一致させる市場のメカニズムです。これがお金に適用されると「金利」となります。お金の価格としての金利が上下することで、投資(お金の需要)と貯蓄(お金の供給)は一致するわけです。
ですが、著者によれば、現代の先進国においては、二つの要因で、金利が著しく下がっても貯蓄の分だけ投資が生じないということが生じえます。
それが「追われる国」という要因と「バランスシート不況」という要因です。以下の節で、この二つをそれぞれ見ていきましょう。
資本主義の発展段階論―ルイスの転換点・黄金時代・追われる国
この「追われる国」の問題を理解するには、クー氏の資本主義の発展段階論を理解するのが早道だと思います。
それは①「ルイスの転換点」以前の資本主義の初期段階、②「ルイスの転換点」以後の資本主義の黄金時代、③先進国が「追われる国」となるグローバリゼーションの時代の三つに区分されます。
まず、農村の過剰人口が枯渇する「ルイスの転換点」までが、第一期である資本主義の初期です。この時期、労働者は農村からいくらでも供給されるので、供給過多の状態にあり、したがってどうしても買い叩かれることになります。そのような労働者の環境は悲惨であり、この悲惨さが資本主義の転覆を主張する共産主義の根拠となります。
だが、このような安価な労働力を使って企業がどんどんと生産を拡大していくと、遠からず農村の過剰人口が枯渇する「ルイスの転換点」に到達します。すると労働者の需給が逼迫してくるので、その賃金は上がらざるを得ないし、全般的な待遇も改善されていきます。
これが戦後の先進国の高度経済成長の時期、第二期となる資本主義の黄金時代です。労働者の賃金上昇は、企業にその賃金を賄うだけの生産性向上の工夫を強いることになり、その工夫で可能になった大量生産で作られた商品を、賃金が上がった労働者が買っていき、その旺盛な消費がさらなる大量生産とそれによる生産性向上、そして賃金上昇につながっていくという好循環が生まれました。
この時代は家電製品や自動車などの耐久消費財が飛ぶように売れ、一般の人々の生活に革命的な改善が起きた時代でした。この労働者の境遇の改善が、マルクス主義が支持を失った理由だったのです。
しかし、この黄金時代はいずれ第三期の「追われる国」の段階に移行していきます。このように労働者の賃金が上がっていくと、自由貿易を前提とすれば、その国の国際的な競争力は失われていくからです。賃金が安い国の方が安く商品を作れるからです。そして、資本移動も自由であれば、自国の企業も国内ではなく、安く物が作れる海外に投資して工場を作った方が収益率が高いということにもなるわけです。
こうして先進国は、賃金が高い先進国であるという理由で、グローバリゼーションのもとでは不利な状況に置かれます。その国で作ったものが値段の高さのために自国でも外国でも売れにくくなる、つまり、消費されないだけではなく、物を作るための投資も海外に移っていくからです。
これが著者のいう「追われる国」が置かれる状況であり、西洋先進国は1970年ごろから日本の追い上げのために、この状況に陥り、その日本自身も1990年代からは韓国・台湾・中国の追い上げで同じ憂き目にあうことになりました。
こういった状況に置かれた国では、いくらお金の値段としての金利が下がったところで、投資はそれほど増えません。海外で投資をした方が圧倒的に収益率が高いからです。その場合、企業が必要とするお金とは自国通貨ではなく、その投資先の外国の通貨なのです。
利益最大化ではなく債務最小化―バブル崩壊とバランスシート不況
さて、著者が挙げるもう一つの投資不足の要因が「バランスシート不況」です。これはバブルが崩壊した後の状況では、企業は伝統的な経済学が想定する利益の最大化を目標とするのではなく、債務の最小化を目標として行動するということを言っていいます。
一個一個確認していきましょう。
まずはバブルとその崩壊についてです。バブルとは資産価格がいわゆる「合理的水準」を超えて上昇することです。資産価格が上がっているから、みんながもっと上がると思って買い上がっていくのですが、どこかの時点でその上昇への信念が崩壊して、みんなが一斉に売りに回ります。すると資産価格は暴落し、一足先に逃げられた人以外の大半の人は大損を被るということになります。
問題は、ここで多くの経済主体、すなわち、家計や企業のバランスシートが毀損されるということです。具体例で見ていきましょう。
バブルの時期において、家計や企業は借金をして資産を買っていきます。100万円を借金して、100万円の土地を買います。この時点では、資産が100万円の土地、負債が100万円の借金だから、純資産はゼロです。
この土地が200万円になると、純資産が100万円となります。とすると、この値上がりした土地を担保にすることで、より多くの借金が可能になってきます。その借金でまた土地を買います。こういうことを皆がやっていけば、土地の価格は上がり続け、借金も資産もどんどんと増えていくことになるわけです。
問題はバブルが崩壊した時です。このときには資産の方が暴落で小さくなるものの、借金の方は変わりません。そうすると純資産がマイナスの状態、すなわち、債務超過状態となります。すると少なくともいま清算すれば破綻状態ということになりますから、多くの家計や企業はこの状態では借金の返済に専念するようになるのです。
その一つの方法が、土地を売却して借金を返済しようとすることで、この売却はバブルの崩壊をさらに悪化させるという悪循環を生み出します。
さて、この状況においては、筆者によれば、企業の行動原理も伝統的な経済学が想定する利益最大化ではなくなります。債務超過を解消すること、借金を返済すること、すなわち、負債最小化が企業の行動原理となるというのです。
このような状況においては、伝統的な経済学が想定するような金利の引き下げでは投資を促進することはできません。企業はとにかく負債の最小化がしたいのですし、その状況下では、借入コストが少し下がったからといって借金をするなど論外なのです。
以上が、著者による投資不足の二つの要因の説明、「追われる国」と「バランスシート不況」です。
では、それに対して著者はどのような対策を提案しているのでしょうか。第4節では「金融政策から財政政策へのシフト」、第5節では「構造改革の新しい根拠」という観点から、著者の政策提案をまとめます。
金融政策から財政政策へ重点をシフトするべき理由
さて、著者の政策提案の第一は、政府が行う経済政策の両輪をなす金融政策と財政政策について、前者から後者へ重点をシフトするべきだというものです。
その理由は、黄金時代と違って、現代では(1)金融政策は効果が薄く、(2)財政政策は確実に効果があり副作用が小さいから、だといいます。
まず(1)の金融政策について見ていきましょう。黄金時代は、どんどん機能が改善される耐久消費財など飛ぶように売れる商品が多数あり、企業としては次々に投資を拡大して利益を最大化したい時代でした。
こういう時代に危惧されるのは消費や投資の過剰によるインフレですが、このインフレは利上げによって貯蓄の便益と投資のコストを増加させることで、首尾よく防止することができました。
逆に企業の投資意欲が旺盛なので、利下げで金利を引き下げるなら、すぐにそのコスト低下に反応して企業は投資を増やしました。こうして経済がデフレに陥ることはなかったのです。
しかし、現代の先進国においては海外投資の方が収益率が高く、またバブルの崩壊でバランスシートが傷んでいるといったことが多いため、投資は利下げにあまり反応しません。いくらコストが小さくても儲からないなら投資はしないし、バランスシートが痛んでいればさらに借金をしようとは思いません。まずは返済が優先なのです。
こうして金融政策の効果が薄く、追われる国が慢性的な投資不足でデフレ基調のなか、金融緩和が長期化することになります。すると、資金調達コストが低く、資産の割引現在価値が上がるため、バブルが生み出されます。それで「資産価値が上がったことで消費が促進される」といった資産効果によっていくらか景気は回復するものの、バブルはいずれ崩壊します。そうしてバランスシート不況が訪れ、効果の薄い金融緩和が長期化します。すると…。
こういうわけで、先進国ではデフレ→効かない金融緩和の長期化→バブルとその崩壊→デフレという循環が生じていくことになるわけです。
(2)の財政政策に話を移していくと、こうした状況では、金融緩和を通して企業に借入を促す方法は通用しません。それに対して、確実に効果があるのは政府が直接借入して投資を行う財政政策なのです。
ただ、財政政策には財政悪化懸念や、それがその分だけ民間投資を締め出しクラウディング・アウトの懸念が付きまといます。後者の場合、政府支出が増えた分、民間投資が減るから、財政政策はそもそも効果がないことになります。
これに対して著者は、そもそも現代の先進国では上記の理由で民間投資が低調であり、その結果として金利がずっと低いままなのだから、利払い負担による雪だるま式の財政悪化の懸念も、民間投資の締め出しも懸念するには及ばないと著者は反論します。
さらに財政支出については独立で採算が取れるプロジェクトを理想とし、優秀な人材が政治(利権・特殊利害)から独立してプロジェクトを選定し遂行する独立投資委員会の設立を提案しています。独立で採算が取れるなら財政悪化は起こりません。
この辺りの議論は、MMT派の貨幣論を取る私の立場からすればやや物足りない面もありますが、この記事はそれを論じる場所ではありません。
とにもかくにも、こういうわけで、(2)財政政策の副作用は現代においては少ないということになります。
構造改革のための新しい根拠―減税・規制緩和・教育改革
さて、このように金融政策から財政政策へのシフトを唱導する著者ですが、もう一つ推している政策が「構造改革」です。
著者において、財政政策はどちらかといえばバランスシート不況期の急性的な投資不足に対応するものであるのに対して、構造改革は追われる国を襲う慢性的な投資不足に対応するものとされています。
すなわち、海外に対して劣っている企業の投資の収益率を上げることが必要であり、そのためには構造改革が必要だというのです。
ここで著者が言っているのは、とにかくイノベーションを促進せよということで、イノベーターを育て発掘する教育制度、イノベーターの意欲を阻害しない税制、イノベーションを阻害する規制の撤廃などが念頭にあります。
単なる財政緊縮を意味する公的部門の身を切る改革等は、著者のいう構造改革には入っていないようです。
著者が主張するのは、小泉政権下で短期的な景気回復を実現するものと喧伝されて、実際にはそうならずに信頼を失った構造改革という政策に対して、「イノベーションで投資収益率を改善することで追い上げる国の追跡をかわす「追われる国」に必要な政策だ」という新しい意義、新しい根拠を与えなければならないということです。
終わりに―この本の一番印象的な一節を紹介する
最後に本書で一番印象的だった一節を紹介して要約を終えたいと思います。
共産主義は経済がルイスの転換点(LTP)へ向かう工業化の過程で生じる極端な不平等の副産物である。その一方で、国家社会主義を唱える極右政党の台頭はバランスシート不況等への間違った政策対応で生まれた極端な不況の副産物である。つまりナチスの台頭に始まる悲劇を招いた原因は、自分たちの経済がマクロ経済学の残り半分である[借り手不足・投資不足](…)にあることを理解できなかった、当時の政策当局の無能にあったということである。(p.359-360)
これは世界金融危機(リーマン・ショック)後の回復期に早々に緊縮財政に復帰していったユーロ圏の政策の誤りを論じ始めるに際して著者が言っていることです。ヨーロッパは1930年代の過ちを繰り返そうとしているというのです。
この引用は共産主義と国家社会主義(ファシズム)の位置付けが見事で秀逸であるように思います。
これをもう少し私なりに敷衍してみましょう。共産主義はルイスの転換点に到達する前の労働者の困窮から生じます。他方でファシズムはルイスの転換点への到達とほぼ同時か、あるいはむしろその直前に生じたという点が歴史的に極めて興味深いように思います。
なぜこういうことになるかといえば、ルイスの転換点の到達直前とは、一方で農村の過剰人口を使い尽くすほどの生産力の拡大が実現していながら、労働者は低賃金のために十分な購買力を持たないという、生産(供給)と消費(需要)のギャップが極大化した不安定な時期だからではないでしょうか。
だから、1920年代の経済、とくに第一次世界大戦による欧州での供給不足と需要過剰に乗じて一段の成長を遂げていた米国経済は、そもそもバブルによってしか持続可能ではなかったのです。バブルが生み出す多幸感と資産効果が生み出す過剰消費によって、かろうじて供給に需要が追いついていたのであり、バブルの崩壊とともにそもそも大きくなっていた需要と供給のギャップが顕在化したのではないでしょうか。
そして、これに対して積極的な財政出動という対策が即座に打たれなかったことが、恐慌を大恐慌に、そして世界恐慌へと広げていきました。そして、これに対して、理論的ではなく直感的なものではあるものの、それでもやはり当時の状況においては正しかった「反緊縮」政策を持っていたナチスを台頭させることになったわけです。
私がよく使う議論ですが、グローバリゼーションとは資本が再び農村を発見すること、ルイスの転換点以前に逆戻りすることに等しいのです。そのなかで先進国の労働者の購買力は切り詰められ、ファシズム勃興時と同様、再び需要と供給のギャップが開く不安定な時期を世界は迎えているように思います。これは大きな傾向としては2025年の今でも変わっていないと私は思うのです。
そのなかで財政緊縮策を続けることがどんな帰結を生むのでしょうか。それを考えるとしばしば戦慄せざるを得ません。
積極グマと暗渠づたいおじさん余談—「日本はこれから何で食ってくか」問題



「追われる国」とか「バランスシート不況」とかのクー氏のマクロ経済の認識には激しく同意なんだけど、貯蓄が投資されるみたいな又貸し論とか、財政出動するにしても独立採算できた方がいいとかといった財政についての考え方は主流派経済学的な感じで、ちょっと古臭いよね。



うん、まあ僕らみたいにMMTから経済学に本格的に入っていったMMTネイティブからすると、どうしてもそう感じてしまうねえ。



あとは「構造改革」をどう見るか。イノベーションをしてグローバリゼーションに負けないくらい国内の収益率を高めろってことらしいけど。



ここもちょっと古臭いというか、なんかグローバリゼーションを過度に前提視している感じは受けるよね。グローバリゼーションのなかでの競争に勝ち抜けってわけだけど、グローバリゼーションを辞めちゃうということがまったく考えられていないのは、2019年という時代の刻印ということは言えるかもね。
とはいえ、まだいまの日本でも「日本はこれから何で稼いでいくか」「日本はこれから何で食ってくか」みたいな言い回しを聞くことが多いし、あまり批判もされていないようだから、グローバリゼーションの前提視はまだまだ強力かも。
日本を主語にして「何で稼ぐ」「何で食ってく」という人たちは、明らかに日本が他の国と競争して海外で何かを売って市場を獲得していくという国際競争でものごとを考えているけど、これを過度に強調する必然性はないと思う。
だって別に日本は国内で必要とされるものを国内で作るということをやっていけば、海外と競争して海外に対して何かを売って「何で稼ぐ」「何で食ってく」なんて考える必要はないわけで。それが本書の日本語副題にある「ポスト・グローバリズム」の「経済安全保障」的な考え方の行き着く先じゃないだろうか。
もちろん、こういうと「日本は資源がない」という話が出てくるし、そういう意味じゃ資源購入のためにそれに見合う輸出(外貨獲得)がある程度必要であることは僕も認めるけれど、やはり三点ほど言いたいね。
一点目、資源のようなどうしても取れないもの以外は頑張って自給して輸入依存を減らすようにすれば、それほど輸入のために輸出を頑張る必要は無くなるのではないか。少なくとも「日本は何で食ってくか」という言い方をするほどには。
二点目、日本に資源がないというのは本当か。技術革新のなかで、日本にあるものを資源化したり、海底にあるような資源を開発したりすることはできるようになってくるのではないか。それをしっかりやれているか。
この一点目・二点目は輸入を減らせば輸出を頑張る必要はないという話で、どっちに重点を置く方が合理的かという話。輸出を増やすことと輸入を減らすことはある意味で等価なんだ。とすると何か最先端ものを頑張って輸出を頑張るよりも、基本を押さえて輸入を減らす方が合理的である場面はあるんじゃなかろうか。
三点目、日本にはある意味で貯金があるとは言えないか。それがこれまでの貿易黒字の積み重ねから生まれた対外純資産であり、その資産が生み出す第一次所得収支の黒字、それによって貿易が黒字でなくとも黒字にとどまる経常収支ではないか。なぜ貿易が黒字でないことだけを見て、これまでの蓄積とそのおかげの黒字を全く見ないのだろう。
こう考えると、何か日本という主体が、それこそ家計みたいに外で働いて稼いでこなくちゃ何も得られないかのように語るのはミスリーディングじゃないだろうか。国家の財政を家計に例えるのを家計簿脳と揶揄する言葉があるけれど、「日本はこれから何で食ってくか」も有害な家計アナロジーではないだろうか。家計でなく国家である日本は自家生産でかなりの程度やっていけるくらい大きく、ここでも家計のアナロジーは的を外していないだろうか。そんな風に思うんだ。
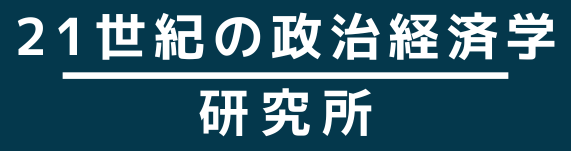


※コメントは最大500文字、5回まで送信できます